イスタンブール話を休止して、友人が本を書いたのでそれをシェアしようと思います。 浅見実花さん『子どもはイギリスで育てたい! 7つの理由』(献本御礼)
彼女とは渡英時期が一緒で(2010年)まず彼女の旦那さんと知り合いになったのですが、家が近所で子ども同士の年齢が近く、お互い3児の母という共通点もあり仲良くしています。 両親も親戚もいない異国の地で私が3人目を妊娠した時、「ここなら3人育てられるよ!」と太鼓判を押してくれたのが彼女。 双子(現在7歳)の下に男の子(4歳)がいて、旦那さんは出張が多く不在がち、専門のマーケティング・リサーチの仕事もしている彼女の忙しさは同じく3児の母である私にも想像に難くないのですが、おまけに本まで執筆していたとは!
この本は日本で上の双子の出産・子育てを経験してから渡英し、次男をイギリスで出産・子育てしている過程で次々に浮かんだ自分の疑問に答えるためにいろいろ調べていくという章立てになっているし、実際に彼女が経たプロセスというのはそうだったのでしょう。 自らの好奇心に答える形で組み立てられるこの本から見えてくるものは『子どもはイギリスで育てたい!』というタイトルから想像されるような個人の異文化体験記ではありません(*1)、21世紀を生きるに当たって普遍的な価値観とは何か、その疑問に真摯に答えようとし社会システムとして仕組みで体現しようとするイギリス社会の姿です。 それはエピローグにこのように現されています(エピローグの引用なのでネタバレっぽくて申し訳ない)。
各章に散らばったディテールをつなぎ合わせ、全体をズーム・アウトしたとき、浮かび上がってくるものとは何だろう。
ひとことで表すなら、それは1人1人の独立した人格に対して払われる敬意なのだと思う。
社会にはいろいろな人間がいて、それぞれに人格があり、尊重される。 それは、妊婦であっても、母親であっても、子どもであっても。 私たちがお互いに、どれほど違っていても。
このことは、先進国に住む我々日本人にとっても、当たり前のように聞こえるかもしれない。 何をいまさらと、呆れられるかもしれない。 しかし、私たちは、本当にそれを理解しているだろうか。 実際にそのように振る舞うことができるだろうか。 言われてみれば当たり前だと感じることと、それが社会で仕組み化され、人々の常識に染み付いていることは、別のことなのだ。
どんなに違っていようと、誰もが公平に扱われること。 1人1人が、そのポテンシャルを発揮するため、支援されることー。 もちろん、問題は山積であるにせよ、このような信念を国家として掲げ、理にかなった、ときに柔軟で創造的なアプローチを考え、実践し、修正し続ける。 それが、現代のイギリス社会の特徴であり、本書で伝えたかった視点であった。
*1・・・タイトルは出版社がつけたそうです。
この内容に触れる前に少し私たちの話を。
私は夫と2人で2010年に「これから産まれる子どもと私たちにとって世界中からベストな場所を探す」というはっきりとした目的を持ってロンドンにやってきました。 2008年から2010年の間はシンガポールに住んでいたのですが、数ある世界の候補都市の中からロンドンを選ぶに当たって経た思考経路は『ロンドンに引っ越します』、『20、30、50年後を想像しながら動く』、『国の価値観と個人の価値観』などのエントリーに書いてあります。 冷静にPros & Consを検討したし、私たちに合わなければまた動けばいい、くらいの身軽さでした。 夫にとっても私にとっても出身地ではないため、多くの人に「あと何年いるの?」と聞かれます。 来た頃は「5年住んでみて考える」と答えていましたが、この1月でちょうど渡英丸6年の今は「あと10年くらいはいるかも」と答えています。
プロフィールに書いていますが、私は、仕事で、留学で、今まで世界のいろいろな場所に住んだことがあります。 実は今まで一番カルチャーショックを「受けなかった」国がイギリスです(*2)。 これは「優雅なアフタヌーンティー」だとか「イギリスは紳士の国」だとか女性誌の表紙を彩る飾り文句のような表層的なことを指しているのではありません。 外国人である私にとって「何だコレ?」と思う日常の現象のほとんどが調べてみると「説明がつく」「理にかなっている」からです。 日本人を含め外国人から酷評される交通サービスや国民医療制度(NHS)も調べてみると重要なところは外していません(*3)。 「あうんの呼吸」も「空気を読む」必要もなくルールが明文化されているので、この地に生まれた訳ではなく文化的コンテクストを共有しない私にとっても理解しやすい、疎外されることもないからです。
また私たちの子どもにとって「パパとママの両方にとって母国である国」というのはこの世に存在しません。 私は日本で生まれ育ち、夫はオーストラリアで生まれ育っているのだから当然です。 その子ども達が「ハーフ」という言葉で呼ばれて特別視されることなく、自分のパパとママは違う文化から来たということを限りなく当たり前であると感じ、そもそも意識することすらない環境で、ポテンシャルをフルに開花できる環境で育てることは私たちの願いでした(*4)。
現代のロンドンは今のところ私たちの期待に応えているのが「あと10年はいるかも」と答える理由です。 そして本著のエピローグの上記引用箇所は私が「この国、あと10年はいてもいいかも」と感じていた感覚の背後にあるものを鮮やかに言語化してくれました。
いまだにイギリス固有の食事は苦手だし、日が短く雨の多い冬もうんざりしますが、前者は自炊すること、後者は冬休みに逃避旅行して残りの冬を「ああ、(旅行が)楽しかった、楽しかった」と言って過ごす、という「現実的な解」で対応しています。 ”There is no better alternative than London.”(別にロンドンはこの世の楽園ではないが、私たちが取れる選択肢の中では一番まし)、つまり消去法です。
*2・・・余談ですが、今までで一番「ここは住めない」と思ったのがモスクワです。 モスクワ中心街の人通りの多い地下鉄駅で警官にカツアゲされたことがあります(→『ロシア – 警察と司法の闇』)。 恐喝された時に警察に駆け込む、というのが普通の法社会で育った人間の感覚ですが、大勢の人が見ている中、警官にカツアゲされたのは衝撃でした。
*3・・・考えるのは得意でもオペレーションが不得意なイギリス。 交通機関の運営という大きなオペレーションは外資系に任せているため、イギリスのインフラはほとんど外資系になっていることは『ロンドン名物2階建てバスが外資経営でも誰も気にしてない』に書きました。 「不得意なことはやらない」という割り切りが実にイギリス。
*4・・・ このブログの底辺を流れる価値観でもあり『’different’と’wrong’』にも書いています。
上記引用したエピローグにあるように、「法の遵守」、「多様性の許容」、「あらゆる人間が差別されないこと」などは先進国にとって当たり前だと認識されているし、日本国憲法にも書かれています。 それが本当に人々の常識として染み付いているか、は別問題です。
本著にもエピソードとして出てきますが、日本では頻繁にニュースになる公共交通でのベビーカー問題、バリアフルなロンドンの地下鉄・電車駅ではベビーカーでの階段の上げ下げに「手伝おうか」と必ずのように四方八方から手が伸びてきます。 その例を日本であげると、よくあるのが「さすが紳士の国」、「イギリスかぶれ」という反応。 ところが手伝う人はベビーカーを見ると無意識で反射的に声をかけ手が伸びているようです。 助けようかどうしようかとか考えている様子はいっさいありません。 彼らにとって、公共交通はみんなのものだから赤ちゃんが利用するのは当たり前、歩けない赤ちゃんにベビーカーが必要なのも当たり前、みんなが利用するのが当たり前の公共の駅にエレベーターもエスカレーターもないのだから利用できるように助けるのも当たり前で、それ以上でもそれ以下でもありません。 「弱者を助けるのがジェントルマン」と思っているフシもありません。 あらゆる人間が公平に扱われる社会の方が生きやすいから、要は「理にかなっているから」(= it makes sense)行っているだけです。 こういうのを「染み付いている」というのでしょう(*5)。
*5・・・このトピックは『赤ちゃん連れの飛行機 – イギリス編』にも書いています。
本著には母乳育児、離乳食、子どもを預けて働くこと、など日英の統計も多く出てきますが、決して育児の本ではありません。 少なくても私には、育児よりもっと大きな視点を捉えた本です。
それでも、
– 階段だらけの駅、授乳施設などない商業施設、でも街の中がベビーカーで溢れているのはなぜか?
– 高額の保育料(1人フルタイムで預けると月額20万円以上)にも関わらず、大多数の母親が復職するのはなぜか?
– 「年老いた親を養うことについてどう思うか?」という質問に対して「どんなことをしてでも親を養う」と答えた若者は、イギリスが66%、日本が28%。 この差は何か?
– 人口あたりのノーベル賞受賞者数がイギリスが世界一なのはなぜか?
などの問いの答えを知りたいと思ったら読む価値のある本なので、ぜひ手に取ってください!
『子どもはイギリスで育てたい! 7つの理由』
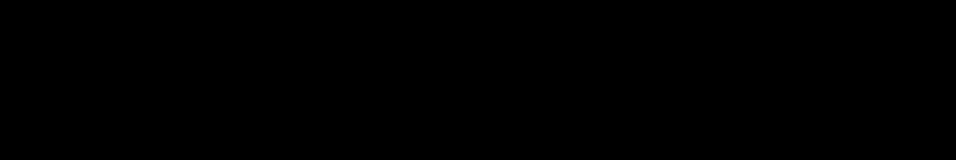

Leave a comment