去年12月にパリから帰ってきた直後に、安西洋之さん(→1, 2)から
ベルサイユの村上隆展はご覧になりましたか?
と聞かれたときから気になってました、アーティストの村上隆(というより”Takashi Murakami”の方が有名)。
実はこの時まで村上隆を知らなかったし、当然ベルサイユ展も見逃したのですが・・・
 安西さんの日経ビジネスオンラインの連載『ローカリゼーションマップ:ヴェルサイユ宮殿に村上隆が連れてこられた』を読んで本人の著書「『芸術起業論』
安西さんの日経ビジネスオンラインの連載『ローカリゼーションマップ:ヴェルサイユ宮殿に村上隆が連れてこられた』を読んで本人の著書「『芸術起業論』買わなきゃ!」と思いつつ、4月の日本で買いそびれ・・・ 作品そのものは右の写真の通り、凡人にはどういう感想を持てばいいのか困窮する展示だし・・・
と、忘れかけていた頃に本展覧会のアート本『Murakami: Versailles』を見つけたので、一気に読破しました。 特に”Le Monde Magazine”記者が行った村上隆のインタビューの内容が実にインスピレーションに溢れています。
普段、ビジネス本ばかり読んでアートに無縁な人、『世界級キャリアのつくり方』とは?とか考えている人にぜひ読んでほしい!
このインタビュー記事、JBPressにほんのちょこっと抜粋されていますが(→『パリで大激論、村上隆・ベルサイユ展覧会』)、全文ネット上に見つからないので、思い出せる範囲で箇条書きします。
私は日本ではアーティストとして知られていない。 『ベルサイユのばら』というマンガのおかげで、ベルサイユ展のことが広まった。
日本でのコンテンポラリーアートは、ヨーロッパでのアメリカンフットボールのようなもの。 興味がない。 たいていの日本人にとっては、意味のないものだし、知る必要性も感じない。
日本人は第二次大戦の敗戦国のメンタリティーで自らのアイデンティティーを問うことをしない、質問を避けてきた。
アメリカとイギリスは戦勝国だから、ポップカルチャーは文字通り”pop up”(はじけて)きた。 焦土と化し、大辛酸を舐めた日本は違う。 一度も文化が”pop up”(はじけて)きたことなんかない。 これを僕は”superflat”と名付けている。
自分の感情を表現するアーティストもいるけれど僕は全く感情は入れない。 インスピレーションの源は日本の美術史をシュールレアリストのスタイルだ。
だいぶ前、「日本の技術ベンチャーは初めから世界市場を目指せばいいのでは?」って話を書いたのですが(→『Red Herring 100 Asia』、『日本のベンチャーよ、世界を目指そう』)、村上さんは初めから世界を見てたことがよくわかるインタビューでした。
だって日本にコンテンポラリーアートの市場がないんだもの・・・(上記引用参照) そりゃ、そうよね・・・
 展覧会の写真だけ見てよくわからなかった作品も『Murakami: Versailles』
展覧会の写真だけ見てよくわからなかった作品も『Murakami: Versailles』で説明文を読みながら見ると面白く、例えば左の”Kinoko Isu”。
スツールになっているこのキノコ型の椅子は、家具が一切ない宮殿内で異彩を放っており、日本人にとっては悲惨な記憶である原爆のきのこ雲や水木しげるの妖怪のひとつ百目にヒントを得たとか・・・
この説明を読んで、「ふーーーん・・・」と現代の日本の側面とフランス貴族時代の象徴のマリアージュ(あえてフランス語、笑)の妙にうなる観客を想像したり。
「世界市場における(自分のルーツである)日本というエッジの利かせ方」において、あまりにも発見の多い本でした。
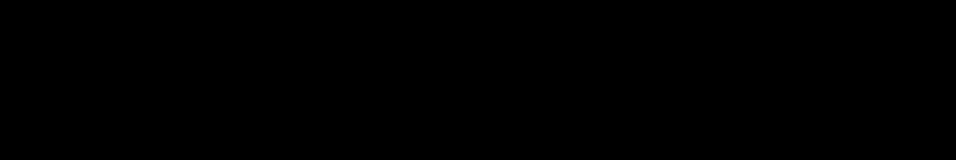

July 28th, 2011 at 11:59 am
村上隆はルイビトンとコラボしたりと、フランスでは有名のようですね。
ベルサイユでのこの企画展については賛美両論だったと思います。
私が一番納得いった意見が
”一生懸命お金を貯めて産まれて初めて憧れのベルサイユ宮殿を見に来た者が、
この企画展をみて満足するだろうか
いつものベルサイユ宮殿が見られなかった事に失望するのではないだろうか。”
と、こんな感じのコメントだったと思います。
お金を貯めて日本文化に触れる為に来日した外国人が、
ポップアートに彩られた
”厳島神社”や”金閣寺”や”奈良の大仏”を見て失望するという感覚でしょうか?
August 8th, 2011 at 1:12 pm
>sunshineさん
>一生懸命お金を貯めて産まれて初めて憧れのベルサイユ宮殿を見に来た者が、
>この企画展をみて満足するだろうか
>いつものベルサイユ宮殿が見られなかった事に失望するのではないだろうか。
すべての人を満足させることは不可能なので、何かを選ばなければいけないですよね?
ベルサイユのような空間を単に往時の姿のまま留めておくのではなく、現代アートのギャラリーとして利用することで、現代に生きるスペースにしようという試みは個人的には大好きです。 フランスのアバンギャルドさ、ここにあり!、という感じ。