渡辺千賀さんの『海外での仕事に必要な英語のレベル』エントリーの図を見ながら「英語力って実は線じゃなくて面、どころか果てしない立体の塊なんだよなー」と思い出したと同時に、「日本人が”英語力がない”と思っているのは実は他の力のことであって”英語”ではない」と私が常々思っているというお話(なお、この千賀さんのエントリーは「仕事に必要な」と限定しているし、ブログという平面上での表現なので直線なのかも)。
私の日常生活はオンもオフもほぼ英語。
それでも公立中学の義務教育が英語に触れた初めての機会で帰国子女でもなく英語を「外国語」として学習した身で、English native相手に(コンサルという)しゃべるのが仕事みたいな稼業をやっていると落ち込むことは数限りなくあります。
この一生かかってもたどりつけないという軽い絶望感は、身に覚えがある人が多いのでは?(ちょっと古いけど、lat37nさんの『それでも英語は難しい』エントリーもそう)
私はシンガポールに越してきてすぐくらいの時期に、「英語コンプレックスは持たない」と決めました。 だって、今後おそらくずっと英語を最もよく使う言語として生きていくのである、そんなコンプレックスを持ってしまったら一生それを背負わなくてはいけないではないか・・・
こういうのは心の持ちようなので自分で決めるものだと思います。 その代わりに「英語力」という漠然とした捉え方をするのではなく、その中身を分解して攻略することにしました。
基本的に次のように分解できると思います(かなり努力して英語を勉強し実践も経た人を想定しています、もちろん絶対的に必要な基礎力というのはありますが、ここでは割愛)。
1. ボキャブラリーが足らない
上で「英語力は線ではなく立体的な塊」と書いた所以ですが、ボキャブラリーは分野ごとに塊・塊で増えていきます。 英語で中等教育を受けていないGMAT(ビジネススクール入学に必要な試験)受験生はGMAT Math(数学)の単語がわからないうちはお手上げなのに、単語を暗記した途端に満点が取れてしまうのは典型例。
そして、この巨大な塊の感覚としては、以前『(今度こそ)英語学習法 – 1』で紹介した渡辺千賀さんのこのエントリーの
相手は氷山、私はドライアイス
という感覚が最も近いです。
最近、医者に行ったとき、ワンセンテンスに3つくらい知らない単語が出てきて我ながら驚愕しました。 ワンセンテンスに3つって何もわからなかったに等しい。 それなのに隣にいる夫は全部理解しているではないか・・・
氷山を前にドライアイスが頑張ろうとするのも気が遠くなる話ですが、そういう場合は『(今度こそ)英語学習法 – 2』で紹介した本田直之さんの『レバレッジ英語勉強法』にあるように、自分の利益になる特定分野だけ集中的にボキャブラリーを覚える方法がいいでしょうね。
2. 発音・アクセントが聞き取れない
CNN、BBCなどきれいな英語が聞き取れるようになれば、後は英語力ではなく慣れの問題(人によって「耳がいい、悪い」という得手・不得手はあるようですが)。
English nativeの夫より私の方がインド人英語のヒアリングが得意なことを発見したときは嬉しかったです(以前、インド人と一緒のプロジェクトにいたからか?)。
また2人でTVを見ていてスコットランドや北イングランドの強いアクセントの英語に「今何て言った?」「ぜんっぜんわかんなかった」と顔を見合わせることもしょっちゅう。 よって、「英語力」ではないです、慣れの問題。
『これからの時代の伝わる英語』に書いたように、「まずは聞けなければお話にならない」のでとにかく聞いて、聞いて、聞きまくることが必要。 スポーツと一緒で反復練習あるのみ。
3. もあるのですが、長くなってしまったので明日。
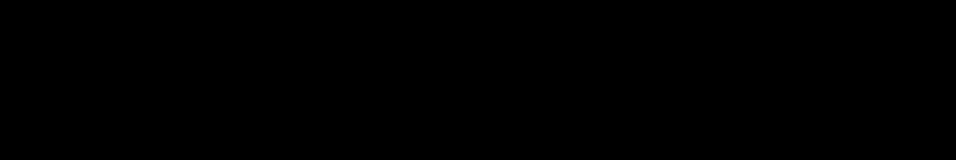

January 6th, 2010 at 4:14 pm
ボキャブラリーは大事ですよね~。
あと、青年期までに抽象思考や論理思考を鍛えていない人には、難しい内容のやりとりは母国語でも厳しいのではないかと思います。
高度な抽象思考をするためには、ネィテイブ・ランゲージで基礎教育を受けた後に、複数言語を学び、特に意味論と長文の構文構造理解のトレーニングが欠かせないように思います。
Dr.Henry KissingerやDr.Zbigniew Brzezińskiなんかともに東欧からの移民で英語の発音はけっこうなまってますが、超微妙な政治問題を慎重に言葉を選んで表現しています。 ロジックと意味論が重要でしょうね。
慣れの方は、最近は、youtubeとかInternetも発達したのでやろうと思えば日本でもEUでも中国でも、小中学生くらいからでもずいぶん力をつけやすい環境にあるのではないでしょうか。
January 6th, 2010 at 9:27 pm
la dolce vitaさん、
外国語についてのエントリーをしようとして先を越されてしまいました(笑)。日本語でのコミュニケーション能力の高さと外国語の壁、みたいなことをボーっと考えています。Economistにあった、「どの外国語が一番難しいか」を読んでいたのが切っ掛けです。ちなみにスペインでは、「悪い事をした奴には罰としてバスク語を習わせろ」と言われるくらい、バスク語は難しいようです。ラテン語のことも少し書かれていましたが、それを上回るらしいです。
前も少しコメントしましたが、語学というのは本当に時間との戦いですね。自分の現在の水準をビジネスレベルに上げるためには、まあ一年から二年は語学だけで日本語が全くない生活をしないと駄目かな?と思っています。今の水準(電話会議でも半分以上分からない事がある)で給料を貰っているのが奇蹟か?と思うこともしばしば。軽い絶望どころではなく、「もし英語をまともに使えるようにするには、その他の人生の楽しみは全部犠牲だな」と思っていて、呆然としてしまいます。それが「ドライアイスが見上げる氷山」なんでしょう。その呆然さと戦ってへとへとになりながらiPodで毎日CNNを聞く毎日です。
January 6th, 2010 at 9:53 pm
あけましておめでとうございます。
フランス語の先生が、最初のクラスの時に、
「言語を習得するのは、スパイラルだ。直線的に向上するのではなく、螺旋を描きながら緩やかに上達するんだ」と言われて、妙に納得したのを覚えています。
今年も素敵なブログを更新されるのを楽しみにしています。
January 7th, 2010 at 1:40 am
(今更ですが)あけましておめでとうございます!
いやー、長らく潜ってましたw
英語のみならず、全ての言語において、僕はコンプレックスを持ってますね。
基本的に僕、日本語も苦手なんですよね。
母国語が得意でない人って、やっぱ何語をやってもダメっすよね。言語能力が著しく低い。。
どの言語であれ、仕事で話せるかどうかは、結局どれだけ業界用語を知っているかってことですよね。
僕の仕事はIT業界なので、ご存知の通りIT用語は結構世界共通だったりします。
(というかほとんど英語。日本語もカタカナばかり)
ただ、ITでも勿論得意分野、不得意分野があるので、不得意分野になると日本語でも何言っているのかサッパリです。
それこそワンセンテンス内に3単語ぐらい知らないキーワードが出てくることも。
あ、今、バハサインドネシアを勉強中ですが、今まで勉強した言語の中では比較的簡単そうです。(発音や文法が特に)
ただ、こっちにいる日本人はほんと皆仕事でもそのまま使っているぐらいしゃべってて、しかも最初の数ヶ月である程度話せるようになったとのこと。(で、そこからはほとんど伸びてないらしい)
僕は既に2ヶ月弱経ちましたが、いまだ数字と行きたい場所を言えるぐらいです。。
そんな感じで長々となりましたが、またちょくちょく出現させてもらいます!
それでは今年も宜しくお願い致します。
January 7th, 2010 at 3:38 am
まったく同感のエントリーです。
海外でサバイブしていくために、言語のコンプレックスを持たないというのは、他の言語圏でも通用すると思います。
日々片言フランス語で変な汗をいっぱいかきながら仕事をしていますが、言葉に対してコンプレックスを持ったらそこで終わりだ、と開き直ることにしています。打合せ中、発音等でどうしてもフランス語が通じない場合は「申し訳ないのですが、ここは100パーセントの相互理解を目指したいから、英語で説明させていただきます」と開き直って英語で話したりします。フランス語ができないからと縮こまって、何も伝えられないでいるよりは10倍マシです。
続きを楽しみにしています!
January 7th, 2010 at 9:02 am
>Blondyさん
>青年期までに抽象思考や論理思考を鍛えていない人には、難しい内容のやりとりは母国語でも厳しいのではないかと思います。
ふーむ、これ(↑)を青年期(というのはundergraduateくらいまで?)までに意識してやっている人はほとんどいないのでは、と思うのですが、意識しなくても鍛えられているものなのでしょうか? どうすると意識して鍛えることができるのでしょうか?
>ドイツ特派員さん
>軽い絶望どころではなく、「もし英語をまともに使えるようにするには、その他の人生の楽しみは全部犠牲だな」と思っていて、呆然としてしまいます。
たしかに言語習得は若いに越したことはないですねー、私が中国語をさくっとあきらめた所以でもありますが。
1. 本気でやって高みを目指す、2. 旅行で楽しめる程度で満足する、3. 全然やらない、の3種類しかないのでは、と思っています。 新年の抱負みたいに軽く「今年は中国語!」とか言う人多いですけど。
>sunshineさん
あけましておめでとうございます。
>「言語を習得するのは、スパイラルだ。直線的に向上するのではなく、螺旋を描きながら緩やかに上達するんだ」
スパイラルですね、なるほど。 また速度も一定ではなく、まるで停滞しているかのように思えることがあっても実はその期間も重要、ということもありますね。
January 7th, 2010 at 9:21 am
>まつーらさん
あけましておめでとうございます〜
>今、バハサインドネシアを勉強中ですが、今まで勉強した言語の中では比較的簡単そうです。(発音や文法が特に)
インドネシア語は世界でも最も簡単な言語のひとつと読んだことがあります、マレー語に似てるんですよね、たしか。
>僕は既に2ヶ月弱経ちましたが、いまだ数字と行きたい場所を言えるぐらいです。。
いやー、がんばってくださいよー インドネシア人とインドネシア語でしゃべれるなんて格好いいじゃないですか〜
>DODOLELAさん
>日々片言フランス語で変な汗をいっぱいかきながら仕事をしていますが、言葉に対してコンプレックスを持ったらそこで終わりだ、と開き直ることにしています。
いやー、英語以外にもう1言語で働くってすごいですねー 英語でいっぱいいっぱいですが。
その不足を補って余りあるわかりやすい能力があればラクなんですが(だからエンジニアなど理系はラク)、そのようなわかりやすい能力もないのでその底上げもしなければ・・・
January 7th, 2010 at 9:28 am
最近読者になりました。よろしくお願いします。どれも興味深いテーマでお気に入りにさせて頂きました。私は外資系証券で働いてますが、仕事上での英語コンプレックスが入社当時からずっとあります。電話・テレビ会議も正直毎回必死で、周りが笑っているのにそれが分からなかったなんていう事もよくあります(はぁ~)・・。でも今回のお話はまさに目から鱗!そうですよね、「コンプレックスは持たない」!なんで気づかなかったんだろう・・。私が悩んだ結果、今はボキャブラリーを増やす、シャドーイング、リスニングはもちろん、プラスアルファ、口(唇)と舌の筋肉を鍛えています。ゴールなんてありませんが、少しずつ効果はあるような気がします(希望含め)。。。またのupdate楽しみにしています。
January 7th, 2010 at 1:03 pm
>Blondyさん
>青年期までに抽象思考や論理思考を鍛えていない人には、難しい内容のやりとりは母国語でも厳しいのではないかと思います。
>ふーむ、これ(↑)を青年期(というのはundergraduateくらいまで?)までに意識してやっている人はほとんどいないのでは、と思うのですが、意識しなくても鍛えられているものなのでしょうか? どうすると意識して鍛えることができるのでしょうか?<
Dolce vita さんへ
良い質問ですね。
頭を鍛えるほんとの鍵は数学、それも幾何学です。これを意識して学んだかどうかで大きく差がつきますよ。 意識しなくても幾何学ができる人は別ですが。
私はメンターの天才博士によく、数学がよくできない者に難しいことが解るわけないだろ~ とお叱りを受けてます。
BC.387 年にプラトンはアテネに研究教育機関アカデミーを創設しましたが、このアカデミーの入り口には「幾何学を知らざるもの,ここに入るべからず」と刻んでありました。
P.S. 英語版のブログ始めたので覗いてみてくださいね~
January 8th, 2010 at 9:54 am
>ckさん
>電話・テレビ会議も正直毎回必死で、周りが笑っているのにそれが分からなかったなんていう事もよくあります(はぁ~)・・。
私もジョークに笑えないことなんてしょっちゅうですよー そんなときも笑えない理由を分解して考えるようにしています(嘘です、そんなこといちいちしてない。 でも別に笑えなくてもいいジョークもありますしね・・・)
コンプレックスは気の持ちようですよ!
>Blondyさん
>頭を鍛えるほんとの鍵は数学、それも幾何学です。
幾何学ですか。 考えたこともありませんでしたが、大学受験レベルであれば数学は得意でした。 でも数学を極めようとする人って別次元というか、どうすればそんな抽象的なことに興味が湧くのか疑問というか・・・(私、具体的なことが好きなので)
ブログ、YouTubeがたくさん貼ってあって面白そうなので、じっくり覗かせてもらいます!
January 8th, 2010 at 10:38 pm
la dolce vitaさん、
コメントにも書かれているように、正直向いていない人は語学には手を出さない方が良いと思っています(以前も少し言いましたが)。別に語学に限ったわけではないのですが、明らかに人より時間が掛かる人、幾らやっても聞き取りが出来ない人、どうやっても語彙の増えない人は居るわけで、そういう人は最初から外国語を使った仕事はしない方がいいでしょう。そういう人は「通じればいいんだよ」というレベルに行くのでさえもう可哀想なくらい時間が掛かってしまうんですね。逆に「2ヶ月も現地に居て聞いていれば充分に意思疎通できるようになる」という梅棹忠夫クラスの天才も居るわけで、人間の持っている才能の差に唖然とします(しかし自分で書いていて情けないなあ)。
私としては、「旅行で楽しめる程度」ではなく、「自分の伝わる外国語の限界で努力する、駄目ならその仕事は辞めざるを得ない」ということかな、と思っています。どうしたってコンプレックスというか恐怖心は拭えませんね、今でも。日本人には辛い世の中です。
と、こんなところで書いている場合ではないのですが(笑、汗)。