昨日の続き。
ブラック・スワン(= ほとんどありえない事象、誰も予想しなかった事象)が現れやすくなったこれからの時代の身の振り方を考えます。
昨日は1.家計の資産形成、しか書けなかったので、今日は他の側面も考えてみることにトライ。
2. 個人のキャリア
本書では「月並みの国」の住人と「果ての国」の住人の例を以下のようにあげています。
月並みの国・・・歯医者、コンサルタント、マッサージ師、など。 一定の時間で面倒を見られる患者やお客の数は限られるため、稼ぎが何倍にもなったりはしない。
果ての国・・・アイデア人間。 作家、起業家、など。 本を100冊売るのも、1,000万部売るのも、書くことにかける労力は変わらない。 うまくいけば(= 良いブラック・スワン)自由時間がたっぷり取れるが、「果ての国」の性質上、一握りの人間がすべてを得る(Winner takes all)。
『金持ち父さんのキャッシュフロー・クワドラント』的に言うと、「月並みの国」の住人がE(employee = 従業員)やS(self-employed = 自営業者)であり、「果ての国」の住人がB(business owner = ビジネスオーナー)やI (investor = 投資家)でしょうか。
ただ、この点については、キャッシュフロー・クワドラントのことを書いた頃から私の考えも変わり、自分の好きなことをするのが結局一番幸せなのかな、と思います。 結果、それがE(employee = 従業員)やS(self-employed = 自営業者)であっても、夫婦という単位や資産運用など別のところでリスク分散すればいいかと。
3. 国家戦略
個人のキャリアよりむしろ「ああ、そのとおり」と思ったのが国家戦略。
アメリカってのは非常に単純化して言うと、自国を「果ての国」にした結果出る、良いブラック・スワンに前途を賭けている国だと思います。
ついにPC版OSで真正面からMicrosoftに戦を仕掛けたGoogleはブラック・スワンの例で、アメリカはああいうとてつもないものの出現に賭けているし、これからも賭け続ける、たぶん。
『フラット化する世界』のThomas Friedmanが最近The New York Timesのコラムで“Invent, Invent, Invent”と題して、
Now is when we should be stapling a green card to the diploma of any foreign student who earns an advanced degree at any U.S. university, and we should be ending all H-1B visa restrictions on knowledge workers who want to come here. They would invent many more jobs than they would supplant. The world’s best brains are on sale. Let’s buy more!
今こそ米国の大学で院卒以上を取った外国人学生にグリーンカードを与えるべきだ、そして米国に来たいと願う知識労働者へのH-1Bビザ規制をやめるべきだ。 彼らは雇用を奪う以上に雇用を生み出す。 世界随一の頭脳が売りに出ている。 もっと買おう!
と提言しているのを読んで「アメリカってこういう国だったなー」と思いました。
ナシームが本書で日本についてほとんど書いてないのですが、わずかながら書いている内容がこれ。
ボラティリティーを嫌う代わりに吹き飛ぶリスクをとっている。 だからこそ大きな損を出した人は自殺したりする
日本の将来について悲観的な論説は巷に溢れているので、最近なるべくポジティブに書こうと心がけているんですが、これに関しては同意です。
ボラティリティーかー 私も昔はよく「リスク・テイカー」とか言われたけど、ずっと動き続けてると慣れちゃうんですけどね。
何かに挑戦して失敗したとしても命まで取られるわけでなし、路頭に迷うわけでもなし、痛い思いは早めにしよう、と改めて身を引き締められた本でした。
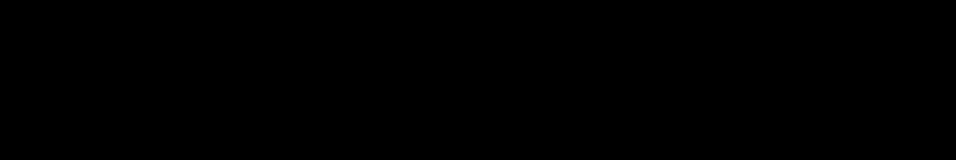

July 12th, 2009 at 6:59 pm
la dolce vitaさん。
「果ての国」ですけれど、これは財務的な意味ではなく、ビジネス的な意味での「レバレッジ」が有効に働くものとも言えないでしょうか?
先日、「ビジネス上のレバレッジはキャッシュフローに結びつきやすいので、ビジネスモデルを考える上での一つのキーワード。」という話を聞いた所でもあります。挙げられていた例としては、
ソフトウエア、本:複製による劣化がなく、複製のコストが安い。
テーマパーク:一度設備投資すると、昨日入場した人と、今日入場した人が楽しむものは同じ。
というものがありました。これは、任天堂とオリエンタルランドの事でもあり、ちょうど両企業とも直近では過去最高の業績をあげていたと思います。
July 13th, 2009 at 9:03 am
>MIKIさん
>「果ての国」ですけれど、これは財務的な意味ではなく、ビジネス的な意味での「レバレッジ」が有効に働くものとも言えないでしょうか?
そうですね、テーマパークやエアラインは設備投資が莫大な上に許容人数に上限があるので???ですが、ソフトウェアや本は複製コストが安く実質複製の上限がないですね。