 週末は長男の4歳の誕生日だったので、初めてナーサリー(保育園)のお友達を呼んでうちでパーティーをしました(右は夫の手作りバースデーケーキ)。
週末は長男の4歳の誕生日だったので、初めてナーサリー(保育園)のお友達を呼んでうちでパーティーをしました(右は夫の手作りバースデーケーキ)。
振り返ってみると一番大変だったのは長男が2歳、次男が赤ちゃんのときで(→『一生忘れたくない瞬間リスト』)、あとはそうでもなかった・・・ あー、でもこういう(→『初めの2年の生き抜き戦略』)ブログ書いてたくらいだから単に記憶が飛んでいるだけかもしれません。
子どもの誕生日って一応本人に向かって”Happy birthday to you〜♪”って歌うけど、実態は「自分たち、よく頑張ったねお疲れさん会」であり(そのお疲れさん会をするのにまた疲れるんだけど、笑)、「たくさん助けてくれた周りの人、ありがとう会」なんだと思います。 昔、親に「自分ひとりで育ったような顔するな」と言われて適当に受け流していましたが、今では心底わかります。
こちらの日本人ママ友(3児持ち、夫は不在がち)が常々「日本で3人育てられなかったと思うけど、ここなら3人でも余裕」と言っていますが、双方の実家が遠いため頼れない私でも、確かに育児に「孤独感」がないんですね、ほとんど。
ロンドンの保育費は高額(→『ロンドン保育事情』、今はこれよりさらに値上がりしゼロ歳児のフルタイム保育は月額25万円)、政府の補助はないに等しいので経済的には大変ですが、広く社会・コミュニティにはとても助けられました。
この「社会・コミュニティ」というのに何層かあって、まず見ず知らずの他人。
『フォーク並びを活かした社会』に書いたように、
リソースがある人(ちょっと手を貸せる余裕がある人)が、ない人に手を貸してあげる、今はリソースがない人も数年経ったら余裕ができるのでまた同じことをしてあげる
を自然と実行している人がとても多い。 ベビーカーでの駅の階段乗り降りはほぼ100%通りがかりの人が手を貸してくれるし、カフェでトイレ行くときに店員さんがちょっと子どもをみててくれる、電車で後ろの席の女の子が「いないいないばあ」をしてくれる、など。 ちょっとしたことなのに、ものすごく助かります。
次に地域ベースのサポートグループ。
NCT(National Childhood Trust)というチャリティ団体や地元自治体主催の各種サポートグループがたくさんあり、母乳育児を支援したり、各種プレイグループやサポートグループ(父親、シングルペアレント、祖父母、若い母親、流産・死産経験者 etc.)を開催しています。 私も長男が産まれたばかりの時は随分助かりました(→『Nappy Valleyの日常』)。 この種のサポートグループは経験者が立ち上げて運営しているので、ケアが適切かつ継続的で行政にはできない領域です。
そして最後に行政。
上に「政府の補助はないに等しい」と書きましたが、我が家が補助の対象ではないだけで、低所得者層には保育費の補助や公的住宅(カウンシル・フラット)への入居権があります(貧困対策としての公共福祉の一部)。 日本のように「定職に就いて定収入があるほど認可保育園に入りやすい」のとは逆。
妊娠期間中と産後1年と16歳以下の薬代は無料、医療費は国民医療制度(NHS)で出産含めてイギリス居住者はすべて無料。
他にも、子連れミーティングを許してくれたクライアント、引っ越し荷造りを手伝ってくれたこのブログのオフ会参加者など挙げればキリがありません。
いろいろな人の愛情を受けて育てられた息子が4歳になりました。 母親1人ではもちろんのこと、夫婦2人だけでも育児はできません。 みなさんのおかげです、ありがとう!
そんな折、神奈川でベビーシッターに預けられた2歳の男の子が亡くなる、という悲しい事件がありました。
こういう事件はイギリスでもありますが、悲しいのはこんな怪しい男に預けざるをえなかったシングルマザーの孤独な育児環境です。 4年前の大阪の2児餓死事件を思い出してしまいましたが、20代前半の稼ぐ力も未熟な女性が、小さい子ども2人を抱えてひとりで仕事と家事・育児をするのは普通に無理、絶対無理、です。
まずは、子どもの父親の養育費支払いを強制執行するよう法改正する(それでも支払い能力の有無は問題)。 親や親戚に頼れないなら(今回は頼れなかったのでしょう)、シングルペアレントの低所得層には自動的に生活保護で生活費・公的住宅を支給する以外、子どもを守る方法はないのだと思います(イギリスのケーススタディ:上智大学『ひとり親家庭に対する経済的支援制度と養育費の徴収:イギリスのChild Support制度の試行錯誤を通して』)。
さらにイギリスのようにチャリティ団体など地域ベースのコミュニティが精神的なサポートなど担えればなおさら良い。
少子化で「産め・産め」って言うなら、すでに産まれている子どもを大切にしようよ。
幼い命を奪われたりく君のご冥福をお祈りします。
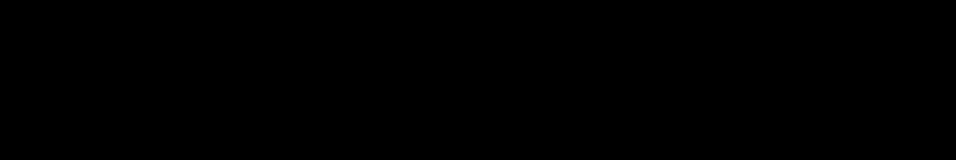

March 20th, 2014 at 8:27 am
今解決しないと、また同じような事件が起こってしまいますね。悲しいことです。ところで、イギリスのコミュニティーはかなり進んでいるんですね。びっくりしました。
April 2nd, 2014 at 7:16 pm
>イギリスのコミュニティーはかなり進んでいるんですね。
子育てしないとコミュニティーに密着した生活はなかなかしないものですね。 他の都市でコミュニティー密着型の生活をしてないので比較できませんが、ちょっとそのネタでエントリーを書いてみますね。
March 30th, 2014 at 1:23 pm
物価の高い大都会での子育てはどこも簡単ではありませんが、ここイギリスは、子供や子供連れに対する社会の目が優しいと思います。先日ロンドンの街中で、バスが急停車したため、子供が乗っていたベビーカーが倒れてしまいました。周りの人がわっと助けに駆け寄り、母親を慰め安心させ、乗り合わせていたイギリス人のおっちゃんは「赤ん坊が乗っているのだから、もっと気をつけて運転しろ!」と運転手に抗議しにいきました。(バスの前に、乗用車が乱暴に割り込んでので急停車は仕方なかったのだけど)
東京では満員電車で通勤する妊娠中のママが赤ちゃんマークのタグを着けるにも、厚かましいと思われたら…と遠慮がちな状況。ロンドンオフィスの妊娠中の同僚は、TFLの”Baby on board!”のバッジをバッチリ胸に着け、「ダサイけど席を譲ってもらえるならいくつでもつけるわ!」とあっけらかん。ここ10年くらいでしょうか、日本(の大都市)では、ルールやマナーを守る、他人に迷惑をかけない、という美徳が行き過ぎたのか、自分達のペースを乱す他人に寛容でなくなってしまっていることがとても哀しいです。先のバスのベビーカー横転事件の後、東京だったら「ベビーカーを畳まずバスに乗るのはやはり危険」「母親がしっかり横で支えているべき」(母親はベビーカーに近い席に座っていた)という感じになってしまうかと思ったりしたのでした。
全ての人に、子供と子連れを積極的にサポートすることを求めるのは難しいかもしれません。でも「しょうがないよね、子供(或いは子連れ、お年寄り、車いす、ネイティブでない外国人、沢山荷物を持っている人)だもの」という寛容さがあれば、もっと子育てしやすい環境になるはず。そういう風土というのは、どうやったら醸成できるのでしょうね。まず制度が変われば、意識も徐々に変わっていくのでしょうか。最近よく考えるテーマです。
April 2nd, 2014 at 7:43 pm
>まず制度が変われば、意識も徐々に変わっていくのでしょうか。
私は制度じゃないと思うんですよね。 日本のムラ社会の特徴とも言える社会の同調圧力がなぜ都会で高まっているのか不思議です。 ロンドンは同調圧力がないですからねー、人種も民族もいろいろな人がいるので、いろいろな人がいるのが当然という意識。
成人で健康な男性に最適化され、弱者に配慮がない社会になってきてますよね。 これが高齢者の割合がもっと増えたらどうなるんでしょう? 高齢者は我が物顔で超マイノリティーの乳幼児連れはますます居づらくなるのかなー?
私もよくわかりません。 ここ7年くらい日本にいないので、どんどん知らない場所になっているという感覚すらします。