少し前にブログネタ切れと書いたら、CREAさんが非常に興味深いインタビューを送ってくださいました。 今年出版された『国をつくるという仕事』で知った人も多いのでは? 元世界銀行南アジア担当副総裁の西水美恵子さんのインタビュー。
ソフィアバンク:Audio Archives 西水美恵子
西水さんは都立高校時代に奨学金でアメリカへ留学して以来、ずっと日本を外から見てきた、ということでインタビューの内容は本当に深く考えさせられるものでした。
経済学者としてプリンストン大学で教えていたのに畑違いの世界銀行へ転身した過程を語った「(1)貧困と戦う世界銀行との出会い」もお薦めですが、「これは聞いておくべき」と思ったのが「(2)今、日本は、何を改革すべきか」の教育に関する箇所(以下、インタビュー該当箇所のサマリー)。
私は教育格差のない時代に義務教育を受けた。 貧しい家庭の子どもでも勉強すればいい学校に行って良い教育が受けられた。 私の行った都立西高はその時代のトップレベルの先生がいた。
その根本が崩れ始め教育格差がつき始めたのが20年ほど前。
世界銀行で取りたい人が見つからなくなった。 海外で仕事や大学に行っている日本人であれば世界銀行で取りたい人材がいるが、日本から直接では欲しい人が見つからないようになった。
この箇所は非常に重要な問題の指摘なのですが、西水さんは2つの問題を一緒にしていると思います。
ひとつは、義務教育過程(最近は高校に行かない人はほとんどいないので高校も含める)における教育格差の問題(= 親の財力が子が受けられる教育レベルに直結する)。
もうひとつは、高等教育(大学・大学院)の質が他先進国(書いてしまうと、アメリカやイギリス)の質に匹敵できないため、世界銀行のように世界トップレベルの学生を採用する組織が欲しい人材が日本で育たない、という高等教育の問題。
ひとつめの問題は、日本だけではなくアメリカ、イギリス、オーストラリアなどでも起っています。
私自身は小・中→公立、高・大→国立、で育っているので、特に小さな頃は地区の公立学校に通い、世の中にはいろいろな人がいることを学ぶことは大事だと思う気持ちが強いのですが、学校内の風紀・先生の質・進学率もろもろの理由により義務教育過程から私立を選ばざるをえないという親が(少なくとも上記の国では)ここ20年くらいの変化で本当に多い。 残念ながら私は全部国公立でもよかった最後の世代かな、とすら思う。
最近もThe Economistでアメリカ・イギリスにおいてトップ大学に入るためには私立高校に通わせざるをえない状況が記事になっていました(イギリス中で私立高校に行くのは7%だが、オックスフォード・ケンブリッジの入学生の40%は私立高校出身)。
The Economist : Learning lessons from private schools
The Economist : Those who can
スウェーデンなどの高福祉国で教育格差を生じさせないまま良い大学に入れる教育が行き届いているのか知りたいところ。
ふたつめの問題、高等教育機関の質について。
世界の大学トップ20を見るとほぼアメリカ、イギリスの独壇場。
QS World University Rankings 2008 : Top 100 Universities
私は高校時代に「アメリカの大学に行きたい」と言ったら親に「日本の会社に就職できなくなるから日本の大学にしなさい」と言われ、その通りにしたわけですが(そして15年前の時点でそのアドバイスは正しかった)、今もし高校生だったらこれだけ情報が手に入る時代、間違いなく英米の大学を目指していたと思います。 ランキングどうこうではなく、その後広がる可能性が全く違うと思う。
アメリカの初等・中等教育がいまいちでも高等教育が世界最高峰である理由は教授陣・学生ともに世界中から頭脳を集めているからに他ならないわけで、そのことに対する決意・気合い・誇りが(イギリスを除く)他の追従を許していないのではないかと思います。 なお、私はこれが非英語圏の大学・大学院にはできないとは全く思っていません。
『未来の歴史とノマドの時代』というエントリーで、
「住みたいところに、トコトコ出向いていって住む」というのが私の基本スタイルですが、子供ができたときに「子供の学齢期にどういう場所(世界の中でどういう立ち位置)にいてあげると子供のポテンシャルを広げられるのか」もよく考えるので。
と書いたら、ブログ内外で密かな反響を得たので、ちょっと教育について書いてみました。
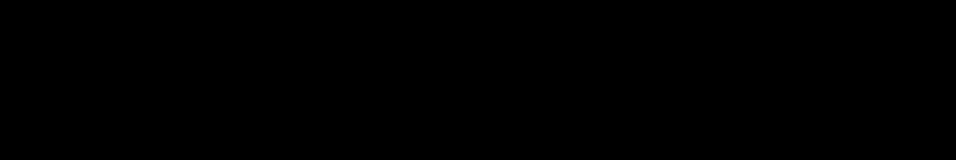

August 26th, 2009 at 12:06 pm
あまり長々とは書かないけれど、Oxfordに来てから子供をOxfordに入れたいと思うようになったし(ただの愛校心というのではなく)、secondary educationもイギリスがいいなぁって。
ただ、OxBridgeに入ろうと思ったら、日本とは比較にならないほどお金がかかりそう。
OxBridgeの入学者のうち私立が「たったの」40%だとは思わなかった。印象としては5歳からずっと私立の男子校・女子高で、中学からは全寮制、みたいなひとたちばかりの印象(単純にそういう人が目立っているだけかもしれない)。
僕の子供は諸事情により公立にすぐ入れなかったので私立の小学校に入ったんだけど(日本では5歳で幼稚園年中だけどイギリスでは小学校1年生)、学費は年間100万円くらいかかったよ(収入がない僕にとっては結構つらい(苦笑))。それでもOxfordの私立では断然一番安い。(それでもひとクラス10人くらいで先生2人という豪華さ)
同級生のご両親はみんなお金持ちばかりで、家の2階だけでバスルームが5つある人とかもいて、びっくりする。
Oxfordの学生は金持ちの家の子がほんと多いよ。
日本とは比べ物にならないくらい身分が固定されていると思うよ。
頑張れば東大、みたいなのはないんじゃないかな。。。
アメリカ人の友達いわく、アメリカの方がまだローンなどもらいながら有名大学に入る可能性が残されているけどイギリスでは無理だろうと。
まあ、データ見ないでOxfordで過ごしてみての印象論で語っているから、大きな誤解かもしれないけど。
August 26th, 2009 at 1:02 pm
私も小中高公立出身です。両親のゆるぎない主義で、葉子さんの上記と同じ理由からですが、これはもう現代社会ではあてはまらないんですよね。私たちの世代の子供はどうするのが良いのか、思案中です。
August 26th, 2009 at 1:34 pm
>AKさん
生情報ありがとう!
>Oxfordに来てから子供をOxfordに入れたいと思うようになったし(ただの愛校心というのではなく)、secondary educationもイギリスがいいなぁって。
日本でもそういう人が増えているらしい、中学からイギリスのボーディングスクールに入れるお金持ち。
上記はインタビューで日本で教育格差がついてきたことを語っていたので「いやいや、日本だけじゃなく他先進国ではとっくにそうなってます」ってことが言いたかったのですが、たしかに日本とアメリカとイギリスとオーストラリアをまとめるのは無理があったか・・・
>OxBridgeの入学者のうち私立が「たったの」40%だとは思わなかった。
40%がどういう数字かわからないんだけど、OxBridgeって留学生は多くないの? 留学生は(たとえ私立高校に行ってたとしても)40%に含まれてないと思う。
あと、金持ちが目立つってのはたしか。 INSEADでも発展途上国から来た人たちはsocialな集まりには全く姿を見せず、自分たちの家で質素に集ってた。 まあ、フランス三ツ星レストラン旅行とかしたがる同級生には私も辟易したので、気持ちはわかる。
>同級生のご両親はみんなお金持ちばかりで、家の2階だけでバスルームが5つある人とかもいて、びっくりする。
イギリスの方が身分は固定されてるんだろうけど、子どもを私立小学校に入れる親が金持ちってのは普通では?
私は、とある大阪の国立大学の付属高校だったんだけど、そこには小学校入学組、中学校入学組、(私みたいな)高校入学組の3種類の人間がいて、後から入学した家庭になればなるほど「普通の家庭」でした。
>頑張れば東大、みたいなのはないんじゃないかな。。。
日本も「頑張れば東大」はどんどんなくなってきてるみたいです(というのは女性週刊誌でポピュラーな話題。 出張が多かった頃、活字なら何でもよくて機内の女性週刊誌をよく読んでた)。 私たちの頃は大アリだったけどね。
>ろちょーるさん
>これはもう現代社会ではあてはまらないんですよね。 私たちの世代の子供はどうするのが良いのか、思案中です。
時代が違うので自分の価値観を押しつけちゃいけないんだろうなー、と思いつつ、でもやっぱりいろいろな人がいるのを知ることは大事だと思うんですけどねー・・・
August 26th, 2009 at 4:25 pm
>40%がどういう数字かわからないんだけど、OxBridgeって留学生は多くないの?
学部生だと15%前後だけ。まあ40%の意味合いを考える上では多いね、確かに。院生だと60%前後かな。
>イギリスの方が身分は固定されてるんだろうけど、子どもを私立小学校に入れる親が金持ちってのは普通では?
まあ程度問題だよね。
たとえば開成高校に通ったら学費そのものは月30,000円台なわけですよ。いろいろ払っても5万円とか。たぶんいい学校に行くには塾とかいろいろかかるのかもしれないけど。
で、僕の息子が通っている小学校は毎年どこの高校に何人合格みたいなデータを出しているけれど、やっぱりイートン校とかに行かせたい親が多いし、実際行っている。
で、イートン校は学費は年間500万円。それプラス音楽とかボートとかの活動に結構なお金をとられる。これが13歳くらいから5年間くらい続くわけでしょ。もう日本とはケタが違う。その差10倍。兄弟二人いたら学費だけで1,000万円を税後で払う。無理です、無理。
でも社会に出たあとの権威としては日本における東大やアメリカにおけるHarvardよりもイギリスにおけるOxBridgeとその他の学校の差は大きいわけで。
まあ日本でもトレンドとしてはお金がないといい学校にいけないとか増えていると思うけれど、イギリスみたいに階級性がないだけマシだと思うよ。僕の地元の名古屋だとさすがに小・中から私立なんて動きは東京みたいにないし。でも東大入れるし。
August 26th, 2009 at 10:16 pm
スウェーデンでは幼稚園から大学まで、一貫して無料なので、
上記の先進国とは全く違ったプロセスが拓かれていると思います。
(phdは、たとえ海外からの留学生であったとしても、生活できるだけのお給料がもらえますし)
また年齢を問わず、いつからでも大学に入り直し、
再学習できる制度が整っているのも素晴らしいと思います。
だからといって、すぐ真似できるわけではないですが。税率も恐ろしく高いですし。
August 27th, 2009 at 9:17 am
思想の違いが教育格差、収入格差を呼んでいるのかもしれませんね。
ちょっと視点がずれるかもしれませんが、
個人レベルでは自分の子供には自分の人生を自分でコントロールできる子になってほしいと思うところです。
お金がないから、教えてもらってないからできないのように「~だから出来ない」ではなくて「こうすれば出来る」と言うように考え、行動するようになって欲しいなと。
自分が出来ることとしては、「親の背中をみて子は育つ」と言いますが、自分が出来ることを子供や子供世代にみせてあげるところから始まるのかなと。
August 27th, 2009 at 9:21 am
>AKさん
>社会に出たあとの権威としては日本における東大やアメリカにおけるHarvardよりもイギリスにおけるOxBridgeとその他の学校の差は大きいわけで。
まあ、これでしょうね、根本の原因は。 社会がOxBridge出身者で支配されている。
これに似て、よく読むブログにも面白い記事がのってました。
http://ukmedia.exblog.jp/12159109/
で、思い出したのが韓国で、韓国の若者は「ソウル大学→Samsung勤務」以外の明るい未来が描けないので若者の閉塞感が強いって読んだ。 極端に選択肢が少ない社会は居辛いのかな、と。
>僕の地元の名古屋だとさすがに小・中から私立なんて動きは東京みたいにないし。でも東大入れるし。
これは、子どもと学校だけ見るとそうだけど、実際、AKさんや私みたいな仕事をしている人が日本で仕事を探そうとしたら東京しか選択肢がないですよね?(もしかして、たまたま一社とかあるかもしれないし、職種を変えればあるけど)
親の選択肢がない以上、子どもが学校に通えることもないので、30年前に名古屋にいて子どもを東大に行かせたサラリーマン層の第二世代は東京に移ってきてるという意味で、「公立に行かせるという選択肢のなさ」は日本も広がってきてると思うよ(この前、横浜のある地区の人が地元の公立小学校から私立中学への進学率75%と言っていた。 「でも埼玉ではまだ公立中学行けるらしい」とも言っていたので、首都圏と言えどパッチワーク状だけど)。
イギリスと比較して、とかではなく時系列的な傾向として(元々、イギリスと比較したエントリーではないので)。
>basilikaさん
>スウェーデンでは幼稚園から大学まで、一貫して無料なので、上記の先進国とは全く違ったプロセスが拓かれていると思います。
「良い小学校」「良い中学校」という格差もないんですか? 無料の大学同士の間での差とかもないのかしら?(日本は国公立の大学の間でもすごいランキングの差があるし)
August 27th, 2009 at 9:48 am
>しんさん
>個人レベルでは自分の子供には自分の人生を自分でコントロールできる子になってほしいと思うところです。
子どもの前に自分がならないと!と思っております・・・
August 27th, 2009 at 5:46 pm
私はまだ国公立は健在であるけれども、私立進学や留学が台頭する先駈け世代だったと思います。(笑)
両親の時代は戦後のナンバースクールの時代で、国立学校は絶対だったことを思うと、今の日本の学校状態は残念です。平等に良い教育が受けれる時代はもうなくなってしまったのだろうな、と。
私はアメリカ在住の2児の母なので、これからアメリカの教育課題に少しずつ足を踏み入れるところなのですが、la dolce vitaさんの書かれたことは身につまされるものがあります。最低限の教育は受けれますが、良い教育にはそれなりの費用を払わないといけないんですよね。(苦笑) ちなみに、そういう状況から、こちらの日本人ママさんの間では、中学校までは色々な教育をむらなく受けれる日本、それ以降は専門性が磨けるアメリカの学校がいいね、などと話しています。
いずれにせよ、どこに行っても自力で人生を行きぬける力のある子供に育てたいな、と努力中。(笑)
これからは、一国内に留まっていては何もできない時代だな、とつくづく思います。
August 27th, 2009 at 6:25 pm
>親の選択肢がない以上、子どもが学校に通えることもないので、30年前に名古屋にいて子どもを東大に行かせたサラリーマン層の第二世代は東京に移ってきてるという意味で、「公立に行かせるという選択肢のなさ」は日本も広がってきてると思うよ
これはいい指摘だな~。そうだね、このトレンドは結構怖いかもね。ちょっと前に東京と地方の人口予測の違いについて触れたエントリー書いたけど、ますます地方との格差が広がる話だよね。
ふと考えたけど、海外で大学入るのに浪人みたいなものってどれくらいあるんだろうね?直感的には少なそう。日本はなんだかんだで、地頭さえよければ最後は1年浪人すればなんとでもなるって感じだけど、そうはいかない国も多そう。Oxfordなんかは共通一次的な試験で点数がいい人だけが面接に進めて、しかも数日間泊まり込みで面接をやって合否を決めるので、勉強だけできれば入れるという話ではないしね。
August 28th, 2009 at 10:02 am
>かんさん
>最低限の教育は受けれますが、良い教育にはそれなりの費用を払わないといけないんですよね。(苦笑)
いやー、ほんとそうです。 私たちの検討対象はイギリスとオーストラリアだけど、私立2人・・・と考えると目の前がくらくらしますね(笑)。
>こちらの日本人ママさんの間では、中学校までは色々な教育をむらなく受けれる日本、それ以降は専門性が磨けるアメリカの学校がいいね、などと話しています。
その場合、中学校(日本)→高校(アメリカ)のステップがうまくいくか、とかいろいろ悩みますよね。 うちは子どもができたらハーフになるので、日本がいいのか、っていうと疑問ですが。
>AKさん
>ちょっと前に東京と地方の人口予測の違いについて触れたエントリー書いたけど、ますます地方との格差が広がる話だよね。
あのグラフと最年少65歳の島の話は本当に怖いです。
大前研一さんは何かの著書で「過疎地の廃村は免れないから公共サービスをだらだら続け(でも段々打ち切る)自然死させるのではなく、計画的に廃村にしちゃって移住させた方がいい」みたいな恐ろしいこと書いてたけどね。
>海外で大学入るのに浪人みたいなものってどれくらいあるんだろうね?
わかんないけど少ないだろうね。 高校の成績(GPA)が結構影響するんじゃなかったっけ?
あと、夫に「早生まれ」のコンセプトを説明してたときに聞いたんだけど、早生まれにあたっても学校にもう1年後の学年にしてもらったり、日本で言う4月生まれになっても学年を1年早めてもらったり、学校の説得さえできればフレキシブルみたいよ。 飛び級とかあるし、あんま年齢関係なく進学過程で自分たちで調整しているのかも。
August 28th, 2009 at 6:33 pm
どうでしょう、中学の差はそんなにないのでは。
と、ものすごく無責任に述べてみました。いや、あくまで個人的感想です、スミマセン。
受験システムも日本とは違って、入学するのは比較的簡単ですし、(←勉強したい人には年齢や国籍その他を問わず、チャンスを与える社会のようです)
経済的要因による教育格差は小さいという印象を持っています。
子供(や自分)の教育にお金は必要ないのが当たり前、というのは、すごい社会です。
30代の友人夫婦には子供が二人いて、貯金もないのに家を買い、車を2台所有してましたよ。
夫婦そろって王立大学のphdで、よく遊ぶし飲むし、月末は財布が空っぽ。
でも彼らが特別なわけではないし、彼らの子供が伸び悩むとも思えないんですよね。
(ちなみに夫の方は、東欧からの移民の息子です)
日本で似たような状況なら、ボロ屋住まいさえままならないでしょう。うーん。
でも、スウェーデンには住みたくないです。寒さと食事の乏しさが。。。
全然関係ないですが、明日は鎌倉へ遊びに行ってきます。
August 29th, 2009 at 7:10 am
私はOxbridge出身者を部下として何人か使ったことがありますが、その経験では彼らの能力が極端に高いという印象は受けなかったですね~。私が鈍感なだけかもしれませんがw
階級社会のイギリスは世界の植民地・コモンウエルスの経営にあたって、それらの国々には基本的に高等教育機関はごく少数しか設けず、植民地経営の中枢を担う人材は全てMetro poleのロンドンで行います。これはと見込んだ人材には良い点をつけて優等の箔をつけて出身地に戻す。
植民地の学制を管理して、植民地での人の採用は基本的に学歴主義を徹底します。
(だからシンガポールなどが、この職には少なくともOレベルのサーティフィケートが要るとかいう学歴社会になっちゃう。)
で、Metro poleの高等教育機関のステータスを高く保って、その教育コストをごく高く設定し、中産階級以下はそのエリート養成コースには簡単に入れないようにしておいて、早期選抜をしつつ奨学金制度を使ってシステムの維持・強化に役立つ人材だけを思想チェックしつつ少数選抜して採用し、卒業生はエリートコースに乗せ高給を保障してやれば、帝国システムを支えるやる気のある優秀な人材を確保できる。
で、こういう人材と本当の上流階級とでネットワーク、インナーサークルをつくる仕組みがしっかりできている。
(例えばローズ奨学金制度:クリントンなんかが良い例
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhodes_Scholarship
http://www.rhodestrust.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cecil_Rhodes )
機会均等主義はあまり発想になく、教育に大金がかかる仕組みを採用して資本の力にものを言わせることができる土壌を形成しているということでしょう。
これを影響力あるメディアの支配と各種顕表制度と合わせるとかなり強力なインフルエンシャルなシステムができるわけですね。
顕著な功績をあげればBBCやEconomist等で紹介され、うまくいけば女王陛下からナイトの称号も貰えますヨ。
でこの植民地経営モデルが、植民地がなくなったあともアングロアメリカンの資本主義システムのコアになっていて、それがグローバル自由市場資本主義の世界化によって現在、従来機会均等主義だった国々も含めて各国におおきな変化を与えているのでしょう。
ちなみに旧日本の植民地経営は、台湾や朝鮮に日本と同様に高等商業学校や大学を作って現地での高等教育に相当金をかけ英国流とはかなり違うやりかたでした。
また明治期の日本には、学部はハーバード、仕上げはボン大学でやったなどという金持ちがけっこういて、彼らは大正から昭和初期に子弟をOxbridgeやIvy leagueなどに入れることが多かったようで、そういうメンバーが東京倶楽部などに集まっていたわけです。白州次郎なんかが第二世代の典型ですね。
P.S. 頭がよく仕事ができて高給が稼げて世界的なインナーサークルのメンバーであるということが幸せかというとこれはまた別問題かもしれませんね。
September 1st, 2009 at 11:55 am
>basilikaさん
>30代の友人夫婦には子供が二人いて、貯金もないのに家を買い、車を2台所有してましたよ。
子どもの教育も老後の心配もないから誰も貯金しないんですよね。
それだけ政府を信用しているところがすごいと思います。 私、全然信用してないからなー・・・他国から行くとマインドセットの切り替えが大変かも。
>でも、スウェーデンには住みたくないです。寒さと食事の乏しさが。。。
全く同じ理由でどれだけ教育レベルが高く高福祉でも北欧に住む気はしないですねー・・・
>Blondyさん
>私はOxbridge出身者を部下として何人か使ったことがありますが、その経験では彼らの能力が極端に高いという印象は受けなかったですね~。
私もOxBridge出身の同級生何人もいますし、今の同僚も夫の同僚もOxBridge出身ですが、特に他の人と比べてどうっていうことはないですねー イギリス外に出てしまえばそんなものなのかも。
>Metro poleの高等教育機関のステータスを高く保って、その教育コストをごく高く設定し、中産階級以下はそのエリート養成コースには簡単に入れないようにしておいて、早期選抜をしつつ奨学金制度を使ってシステムの維持・強化に役立つ人材だけを思想チェックしつつ少数選抜して採用し、卒業生はエリートコースに乗せ高給を保障してやれば、帝国システムを支えるやる気のある優秀な人材を確保できる。
なるほど。 これは一国内だけでは機能してきたかもしれないけど、今のようにグローバルに人材が流動化すると自国外ではそのインナーサークルがあまり役に立たなくなるんじゃないか、と思ってたんですが?
それとも、グローバル規模でのインナーサークル(Harvard + Stanford + OxBridge + …etc.)ができあがっていくのかなー? もしくは各インナーサイクル同士の間で派閥争いができたり?
>頭がよく仕事ができて高給が稼げて世界的なインナーサークルのメンバーであるということが幸せかというとこれはまた別問題かもしれませんね。
別問題でしょうね〜 Peer pressureに明け暮れる人生というのも何だか寂しいなー
September 1st, 2009 at 3:37 pm
>グローバル規模でのインナーサークル(Harvard + Stanford + OxBridge + …etc.)ができあがっていくのかなー?
グローバル規模でのインナーサークルは歴然と存在していますヨ。
ただし、ただHarvard や Stanford 、 OxBridge …etc を出たからとか、そういう学校を出てグローバル企業で世界を舞台に働いたり、政治家として活躍したり学者やジャーナリストとして成功したからといってすぐそこに入れてもらえるというものではな~い。それらはまあ必要条件の一つといったところでしょう。
基本的には、世界的規模の一定の個人資産を持ち、かつそういう世界的な学校(複数が多い)のalumniネットワークに属し、かつTNCのBoardを何社も兼任しているような、グローバルなコアのネットワーカーの目に止まり、優秀だし使えそうだと思われてはじめて、段階的にいろいろなコンベンションやセミナーに招待されたりするところが入口になることが多いようですヨ。そのうちに、一般では売ってていないある名前のグローバル季刊雑誌(発刊数たしか6万部)が勝手に届くようになりますからお楽しみに。。。(まあ、彼らが気に入らないことを言ったり書いたりすれば、すぐ雑誌も送ってこなくなるし、お声もかからなくなりますけど。 )
2月のDAVOSに声がかかったり、コモ湖のThe Bellagio Centerに招待されたり、友人の多くがCFRメンバーだったりするようになれば一人前のグローバリストに近いと言ってもよいでしょうね。
このごろはSuper Classと言うのが流行りですがw
最近では例えば竹中平蔵さんなんかがその良い例かも。彼は日本での業績?が認められて、今やWEFでは理事をやってますからw
P.S.
まあ、こういうインナーサークルのメンバーにならなくても、グローバルに優雅に生きる方法はいくらでもあるので、あくまでこういうのは選択肢の一つですw
September 2nd, 2009 at 9:01 am
>Blondyさん
>2月のDAVOSに声がかかったり、コモ湖のThe Bellagio Centerに招待されたり、友人の多くがCFRメンバーだったりするようになれば一人前のグローバリストに近いと言ってもよいでしょうね。
なるほど・・・全然知らない世界ですねー
「世界級キャリアのつくり方」の著者の石倉洋子さんや黒川清さんのブログを読んでると「今年でダボスも○回目。 はやく若い人に譲りたい」としょっちゅう書いてあるのですが、その「若い人」にはどうやったらダボスに声がかかるのかがわからないんだと思います。
Young Global Leaderってのがありますが、あれが一種の登竜門だったりするのかしら?
頂いたコメント、最後の方切れてますので、もしよろしければ補足ください!
September 2nd, 2009 at 4:03 pm
Young Global Leader はもちろんその一つですが、もっと若いうちからいろいろな機会でグローバル化啓発教育と優秀な人材の一次発掘は行われていますョ。
例えば
The Asia Society
http://www.asiasociety.org/about/mission-history
とか
The World Affairs Council
http://www.world-affairs.org/home.html
とか。
こういうのをコアに、TNCをスポンサーに様々なグローバル交流型のコンファレンスやセミナーが高校生くらいのレベルからいろいろあります。
高校生から大学くらいでそういう国際コンファレンスに選ばれて出席し、錚々たる学歴とキャリアポジションの先輩(例えばハーバードPhDのフィリピン政府高官とか)のグローバル経済礼賛の熱いスピーチを聞かせる仕組みがあるわけです。
で優秀な人材には、あ~君、優秀だね~留学したら? お金が心配? 奨学金が出るかもしれないからここに応募してごらんヨなんて言われて、分野に応じていろんな財団の奨学金を推薦したりします。(まあ、こういう奨学金はいわば上品な賄賂として発展途上国の高官の子弟が貰ったりすることも多いけど。)
それで、特に見込みのある人材にはここらあたりの奨学金が出ます。
Rockefeller Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Foundation
Rhodes Scholarship
http://www.rhodesscholar.org/
で上手くラインにのると途上国出身のハンディがあってもこういう感じのキャリアに進むことができる訳ですw
Rajat Gupta
http://en.wikipedia.org/wiki/Rajat_Gupta
Fareed Zakaria
http://en.wikipedia.org/wiki/Fareed_Zakaria
P.S.グローバル自由市場資本主義以下のしりきれコメントは私の消し忘れです。失礼しました。中身はまた別途書き込みしますね。
September 3rd, 2009 at 9:10 am
>Blondyさん
いやー、ためになります。 詳しく教えて頂きありがとうございます。
以前の最後のコメントは消させて頂きました! また楽しみにしています。
February 2nd, 2010 at 12:52 am
こんにちは!CREAです。こちらのエントリーを読み返してみて質問してみたいことがあるので、遅ればせながらコメントを書いております。
質問:
「仮にla dolce vitaさんが今、大学生当時に戻れて就職活動をするなら、どんな業界を第一志望にお考えになりますか?」
こちらのエントリーの本文には
>私は高校時代に「アメリカの大学に行きたい」と言ったら親に「日本の会社に就職できなくなるから日本の大学にしなさい」と言われ、その通りにしたわけですが(そして15年前の時点でそのアドバイスは正しかった)、今もし高校生だったらこれだけ情報が手に入る時代、間違いなく英米の大学を目指していたと思います。
とあるので、新卒の就職活動に関しても、la dolce vitaさんのお考えは当時とはどんなふうに変わっているのだろうと伺ってみたくなった次第です。。
非現実的な問いかけで恐縮ですが、宜しくお願いします。CREA
February 2nd, 2010 at 8:18 pm
>CREAさん
質問ありがとうございます。
長くなりそうなので、今度エントリーにさせてください。 しばしお待ちを。
February 3rd, 2010 at 1:08 am
la dolce vitaさん、
ありがとうございます!新たなエントリーとして書いていただけるなんて嬉しいです。
楽しみにしております。CREA