大学生の頃、世界で一番好きな都市はロンドンでした。
イギリス帰国子女の友人に影響されていただけなんですが、あの頃の「好き」にかけるエネルギーと情熱がちょっと懐かしい。
カムデンやポートベローで買った古着を着てDr.Martenブーツ履いてOasisやBlurなどブリットポップ聞きながらロンドンに行くためにバイトに励み、少しでも長く滞在しようと安宿に泊まったり大学のサマーコースに行ったりしました。 滞在中もお金がないので、TESCOやSainsburyで買ったパンにチーズを挟んだサンドイッチが基本食、TESCOのスコーンがたまの贅沢。
1980年代のサッチャー政権による規制緩和や構造改革が効果を現し始めた頃だったけど、まだニューヨークに比べるとメインストリームではなくエッジーでアンダーグラウンドな空気が若かりし私の感性にマッチし、足しげく通っていました。
そんなことを思い出したのは、1990年以降のロンドンを時代ごとに付けられたニックネームで振り返ったThe Economistの記事。 とても面白かったので、エッセンスだけ紹介。
The Economist : Reykjavik-on-Thames
以下、サマリーの拙訳。

1990年代、規制緩和「ビッグバン」で金融の中心都市として復活したシティを抱えるロンドンはmanhattan-on-thamesと呼ばれる。
2001年、アメリカで起った9・11をきっかけに移民流入制限を強化したアメリカに代わり、ロンドンに移民(特にイスラム系)が流入するようになり、ロンドンはLondonistanと呼ばれる。 開放政策に対する懸念は現実のものとなり、2005年にロンドン地下鉄・バスで爆破テロが起る。
それでも、経済成長し続ける新興国から移民の流入は止まらず。 とりわけ高級アパートやイングランドプレミアリーグのチームを買う成金ロシア人が集まり、ロンドンはLondongradと呼ばれる。
家賃の高騰は止まらず、ロンドンはグローバライゼーションの中心、世界の首都として束の間の繁栄を楽しんだ。
その時代に終わりを告げたのが2008年。 クレジットクランチが起こり、一部の銀行は国有化され、ポンドは暴落し、失業者が溢れ、経済学者やトレーダー達はロンドンをReykjavik-on-Thamesと呼び始めた。
数年後、ロンドンはどう呼ばれているのだろうか? 世界不況により、ロンドンは1970年代、80年代のようなただのLondon-on-Thamesに戻るのかもしれない。
確かに最近のロンドンの家賃の高騰ぶりは本当に異常で、普通の給料ではQuality of Lifeが保てないような状況だったし、何よりエリアによって暴力事件が増えているのが気になっていました(下記、イギリスは大陸ヨーロッパやアメリカより暴力事件が多いという記事)。
The Economist : Island savages
ロンドンから今週出張で来ている友人によると、シティ(金融街)のセンチメント(景況感)は壊滅的。 でも、家賃も20%から30%くらい下がってきているし、人々がノーマルになってきている、とのこと。
London-on-Thames、いいんじゃないでしょうか?
地に足のついたロンドン、久しぶりに行ってみたくなりました。
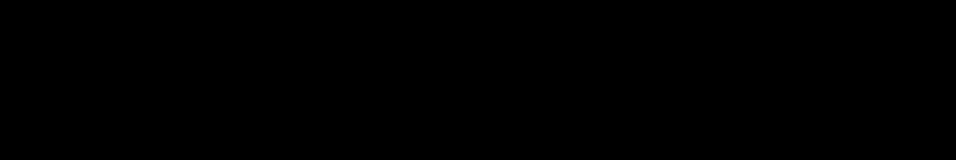

February 20th, 2009 at 4:18 pm
「テームズ河畔のレイキャビック」とは巧く命名しましたね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AF
対外純債務も先進国では飛び抜けて多い:
http://www.spectator.co.uk/coffeehouse/3078296/the-true-extent-of-britains-debt.thtml
February 20th, 2009 at 6:21 pm
FTと英国エコノミスト誌の偏向振り
竹中正治氏による批判:
「世界的な経常収支の不均衡こそ金融危機の根底的原因」?
1) 経常収支黒字諸国での外貨準備の増加とその米国債などへの投資が、現在の米国
を震源地とした世界的な金融危機の根底にあるという主張の代表的な論者は、ファ
イナンシャル・タイムズ紙の経済チーフ・コメンテーター、マーチン・ウォルフ氏
である。
2) 多くのエコノミストにはナショナリスティックなバイアスがある。このバイアス
は政策担当者から新聞・雑誌の読者、TV視聴者まで広く共有されている。自国経
済の失敗の全ては自国の政策の責任であるという厳しい認識を回避しよう、薄めよ
うという傾向は何処の国でもある。そうしたバイアスは最も低俗な形態では「外国
勢力の陰謀説(例、ユダヤ人陰謀説)」などの形で登場する。一方、一見もっとも
そうな経済論的な装いで登場する場合もある。ウォルフ氏の議論は後者の典型と言
えるであろう。
http://www.iima.or.jp/pdf/IER_2009/no1_2009.pdf
February 21st, 2009 at 11:30 am
>snowbeesさん
ありがとうございます。
FTはよく知りませんが、The Economistは自らの政治的スタンスを非常に明確にしており、読者は記事の内容をそのまま自分の意見として受け入れるかどうかを含めて判断することが求められているのだと思います。
それを「ナショナリスティックなバイアス」とは呼ばないと思いますけどね(そもそもFTもThe Economistも英国籍の新聞/雑誌なんですが、書いている記者が米国擁護だからナショナリスティックと竹中氏は言いたいんでしょうか? それとも英国と米国は十把一絡げ?)。
February 22nd, 2009 at 10:36 am
こんにちは!楽しく読ませていただいています。サッチャー政権が改革をゴリゴリやっていた時期に、ロンドンに住んでいました。その後90年代後半にまたロンドンを訪れ、変化に驚きました(景気よくなっている!)。2000年代にまた遊びにいくと、ますますシティの存在感が増していましたね。NHKのドキュメンタリー「沸騰都市」シリーズでも、ロシアの富豪たちがビジネスを求めロンドンに集まってきている様子が描写されていました。2010年代の変化はどうなるのか、楽しみですね。不況になって、新たなWorking Class Heroなミュージシャンの登場を期待するのは、不謹慎かな。
February 22nd, 2009 at 11:16 am
>HelterSkelterさん
はじめまして。
>サッチャー政権が改革をゴリゴリやっていた時期に、ロンドンに住んでいました。
いいですね! ロンドンは今も2年に1回は行きますが、めまぐるしく変わりますよねー 東京もたまに行くとそうなのかな?
>2010年代の変化はどうなるのか、楽しみですね。不況になって、新たなWorking Class Heroなミュージシャンの登場を期待するのは、不謹慎かな。
生まれるかもしれませんね、あの頃のブリットポップは大好きでした。
シカゴGSB、名前変わったんですね。 オバマで随分盛り上がったのでは? シンガポールにもキャンパスがあるので、たまにですがalumniと出会います。