『本で読む育児 – 1』の続き、しつけ・教育(英語で”parenting”)の育児本の紹介です(「明日」と書きつつ時間が経ってしまいました)。 全然まだこの段階の本を読むに至っていないので、みなさまのお勧めやアドバイス・体験談を聞くのが真の狙いだったりします(笑)。
義妹にクリスマスプレゼントでもらったオーストラリアの育児本『Kid Wrangling: Real Guide to Caring for Babies, Toddlers, and Preschoolers』にとてもよく種々のアプローチ・流派(?)がまとめられていたので下記に要約します。 これがすべてのアプローチでもないでしょうし、まとめ方に異議がある方もいらっしゃると思いますが、分類の一例ということで。
1. Raising happy children
ハッピーで快活・自信に溢れた子どもを育てることを第一の目標としたアプローチ。
参照:『Raising Happy Children: What Every Child Needs Their Parents To Know – From 0 To 11 Years』, Jan Parker & Jane Stimpson
2. Attachment parenting(アタッチメント育児)
「母と子の肌と肌の触れ合いは長ければ長いほどよい」とするDr.シアーズのアプローチで、母乳・添い寝・スリングで常時抱くことを推奨。 「抱き癖がつくから」、「わがままに育つから」、と、赤ちゃんが泣いてもすぐに抱き上げない方が良いとするかつての欧米の育児法とはまったく逆の育児法。
参照:『The Attachment Parenting Book : A Commonsense Guide to Understanding and Nurturing Your Baby』, Dr.William Sears、『新編 シアーズ博士夫妻のベビーブック』
、Ask Dr.Sears.com
3. 家族をロールモデルとするアプローチ
親や兄弟・姉妹、親戚など自分の家族の子育てのやり方に頼るアプローチ。
4. 早期教育
子どもの持つ能力を最大限に引き出そうとし、一般よりも年齢を繰り上げて知的刺激を与えること。 早期教育によって幼児期に周りより「発達」した子どもは小学校進学時には学校の授業が退屈になり長期的に利点にならないとする専門家も多い。
5. トリプルP(Positive Parenting Program、前向き子育てプログラム)
オーストラリアで開発され、世界15カ国以上で実施されている親向けの子育て支援プログラム。 子どもの発達を促しつつ、親子のコミュニケーション、子どもの問題行動への対処法など、それぞれの親子に合わせた方法に変えていくための考え方や具体的な子育て技術を学ぶ。
参照:Triple P Japan
6. PET(Parent Effectiveness Training)
アメリカの心理学者Dr.ゴードンが始めたPET(Parent Effectiveness Training、親業訓練)。 アクティブ・リスニングを通して子どもの心を理解し、豊かで暖かい親子関係を築くコミュニケーションのトレーニング。
参照:『Parent Effectiveness Training: The Proven Program for Raising Responsible Children』, Dr.Thomas Gordon、『親業 – 子どもの考える力をのばす親子関係のつくり方』
7. ニュー・エイジ(or ナチュラル)アプローチ
厳しい社会や宗教の規律に反発して生まれたアプローチだが、中身が違うだけで着るもの(オーガニックコットンなど自然素材)、食べるもの(オーガニック食品など)、遊ぶもの(プラスチックのおもちゃは不可)に関し同じように厳しいルールがある。 一般に母乳育児・布おむつ・リサイクル・オーガニック食品・ハーブ療法などが推奨される。
8. 厳しい戒律の宗教グループ
一部のイスラム教やキリスト教は育児法に関しても厳しい規律がある。
9. モンテッソーリ教育
19世紀のイタリアの医師マリア・モンテッソーリによって考案された教育法。 子どもの中の自発性を重んじる教育法で、各国のモンテッソーリ・プログラムを導入した幼稚園で実践されている。
Wikipedia : モンテッソーリ教育
Montessori
参照:『モンテッソーリの教育 0歳 – 6歳まで (1) 』
10. シュタイナー教育
オーストリアの思想家シュタイナーが提唱した教育法。 7歳までは、数字や文字を教えたりせずに、遊びを中心に心と体を創る時期だとしている。 各国にシュタイナー教育を名乗る学校がある。
Wikipedia : シュタイナー教育
All About : シュタイナー教育の理念を学ぶ、シュタイナーの具体的教育法
参照:『子どもの教育 (シュタイナーコレクション) 』
11. レッジョ・エミリア教育
イタリアのレッジョ・エミリア市で行われている地域の共同保育事業。 子どもと大人の双方が創造性を発揮し、美的で探求的な活動をとおして共に学び、育ちあう関わりを形成する教育法。
参照:『子どもたちの100の言葉―イタリア/レッジョ・エミリア市の幼児教育実践記録』
子どもができるって、全く新しい世界に飛び込むことなんですね。 全然知らない世界です・・・
上記のアプローチ、また別のアプローチなど体験談・アドバイスがあればぜひコメント欄にて教えて頂けると嬉しいです。
前回に加え、みなさまから紹介して頂いた本をここにご紹介します。
『おさなごを発見せよ – 羽仁もと子選集』(contentmentさん、yoko3さん)
『絵本とは何か』(contentmentさん)
『赤ちゃんの運動能力をどう優秀にするか – 誕生から6歳まで』(Fumitaka Tamaiさん)
さらにお勧め頂いた本を追加しました。
『定本 育児の百科〈上〉5カ月まで』、『 -〈中〉5ヵ月から1歳6ヵ月まで』
、『 – 〈下〉1歳6カ月から』
(ドイツ特派員さん、私の母)
『ナルちゃん憲法―皇后美智子さまが伝える愛情あふれる育児宝典』(tanupさん)
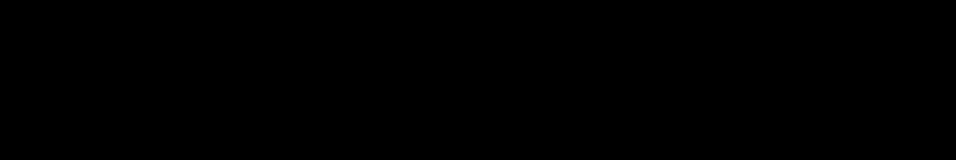

April 4th, 2010 at 2:49 am
la dolce vitaさん、
私、乳児の頃の夜鳴きでも全く起きることなく寝続けて、ずーっと顰蹙買っていました。
で、私の妻が「これこそがバイブルだわ!」と言っていたのが、松田道雄の「育児の百科」ですね。Amazonの書評でも絶賛ばかりというのは珍しいです。残念ながら絶版のようですが、多分日本なら新古書店にはあるでしょう。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4000098500
うちでも、それこそ最初に高熱を出した時、「ああ、もしかすると脳に熱が廻ってバカになるかも」とか心配しましたが、妻が義母(私の母)に相談したら、「そこの横の男(私です)もどんだけ身体が弱くて熱出したか…。大丈夫大丈夫、子供は熱を出すもんだから」と言われ安心したそうです。確かに重篤な病気もあるでしょうが、普通に栄養を与えた普通の子供は普通に育っている、というところがスタートなんでしょうね。
April 4th, 2010 at 8:25 am
育児広場みたいになってますね♪
うちは夫が「子供は子供の部屋で寝かる」スタイルを主張してましたが、夜泣きに負けてすっかり添い寝派になってしまい、1歳10ヶ月も来るとどうにもなりません。私がいないと結構泣きます・・トホ。でも添い寝していれば朝までぐっすりなので、親子でちゃんと睡眠がとれ、日中楽しく過ごせます。
たぶん、1歳前後くらいに寝る儀式みたいなのがだいぶ確立され、おしゃぶりや、人形や、ブランケットなど特定ももので満足して寝れる子なら、一人で自立して寝れるのかなぁと想像するのですが、個性にもよるのかなぁ・・・1人で自立して寝かせるのは、親の根気がいるなーと思いました。夜中1度もしくは2度くらい起こされるたびに抱きに行くのはきつすぎました。日中も忙しいので。
絵本は日英のものいろいろよく読んでいます。
アメリカだとDr. Seussシリーズの絵本が人気みたいですよね。絵本の音の響きも心地よく引き込まれていく工夫がされてるし、登場人物とかもクリエイティビティにとんで子供の想像力を掻き立てる感じで、大人も楽しめますよ♪うちの息子も大好きです♪
日本語と英語と両方の単語をしゃべるようになりましたね。どういう基準で使い分けているのか不思議です。
最近アメリカのママ友に薦められたのが、123Magicというサイトです。子供のしつけに役立つとか。
http://www.parentmagic.com/
DVDとかは見てませんが、フリーのマンスリーニュースレターとかちょっと読むのにはいいかもです。
もうすこし先の育児のヒントがいろいろ見つかるかもせません。
April 4th, 2010 at 9:11 am
うちはシアーズ博士本+桶谷式母乳育児の親子べったり系でいきました。子育てはいろんな宗派があるのでどのやり方がどうのとなんとも言えないですが。子供の様子を見つつペースをきっちり作り上げるBaby Wiseも読みましたが、結局うちにはシアーズ博士本がしっくりきました。
海外組としては日本食材は大事ですよねぇ。特にいい食材は入りにくいし。
April 4th, 2010 at 5:12 pm
>ドイツ特派員さん
>私の妻が「これこそがバイブルだわ!」と言っていたのが、松田道雄の「育児の百科」ですね。
すごい百科ですね、文庫版が3冊組で出ているようなので、こちらのリンク貼っておきますね。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4003811119
>riさん
たくさん情報ありがとうございます♪
>うちは夫が「子供は子供の部屋で寝かる」スタイルを主張してましたが
うちもそうですねー まあ本人がそうやって育ってますから(たぶん)。
私は添い寝で育ってるので、結局どういうスタイルで寝るかでその子の性格が決まるなんてことはないような・・・
>アメリカだとDr. Seussシリーズの絵本が人気みたいですよね。
ありがとうございます!見てみます。 夫はWinnie the Poohとか自分が読んでもらったクラシックなものが読みたいようです。 私は「ぐりとぐら」とか読みたいですねー、やっぱり。
>Kazさん
>うちはシアーズ博士本+桶谷式母乳育児の親子べったり系でいきました。
日本人にはそれが王道なんでしょうか? Routine推奨派はやはり仕事復帰など親の都合が大きな理由な気もしますが、復帰せざるをえない事情もあるわけで難しいところです。
April 5th, 2010 at 1:07 am
私の場合、その頃(息子が生後1ヶ月未満)、全く、育児書を読む余裕(?)すらなかったです。育児書に目を通す時間があるなら、少しでも寝ていたいと思っていたタイプです(汗)。
それで、ここ1年でいろいろな育児書を読むようになりました。Dr. Searsの育児本は日本でも有名ですが、Attachmentが大事と言われても、今の環境(大家族ではない)だと、要求のままに抱っこに応じるのは無理だと思います。今年で息子は4歳になりますが、ご紹介されたTracy Hoggのしつけ編、おしゃべり編は、しっくりきています。
この1年は特に、他のお子さんとの成長具合が気になる場面が多いかもしれませんが、子供も個性が様々で数ヶ月の個人差はよくあることなので、あまり型にはめず、体調に気をつけながら育児もなさって下さいね。
April 6th, 2010 at 7:26 am
yokokloedenさん、立派な育児の大家ですね。(^O^)
私は、子どもが特に最初の乳児の間に「この世の中は安心できる場所なんだ」と感じられるようにすることが大事なのではないかと思い、六カ月間の育児休暇中はとにかく、安心感を与えるように心がけていました。お腹が空いたり、おむつが汚れたり、1人にされたり子どももわけのわからない不快、不安な状況に置かれるわけですが、最終的にはだれかに抱きしめられ、愛情を与えられるという「安心感」「信頼感」を得ることはその後の人生においてすごく大切なのではないかと思います。
それから子どもの仕事は「模倣」ですね。親(あるいは周囲)がよく微笑みかける赤ちゃんはよく笑うというのをまわりの子どもを見ていて実感します。私は笑顔があまり得意ではないのですが、主人及び主人の家族の笑顔のおかげで、うちの子は(親の私が言うのもなんですが)チャーミングな笑顔の持ち主です。それを戦略的に使っているのはどうかと思いますが・・・ あと、夫も私もよく話かけてました。特に私は最初から1人の話し相手として話しかけています。生まれた時から私の良きパートナーになってくれています。
添い寝で思い出しましたが、美智子様の育児について書かれた「ナルちゃん憲法―皇后美智子さまが伝える愛情あふれる育児宝典」も美智子皇后の愛情と細やかな目配り、参考になります。美智子様は添い寝はしない派でしたが、私は仕事をもってほとんど1日じゅう子どもとは一緒にいることができないので、寝る時くらい一緒にと思い、今でもまだ添い寝です。子どもだけでなく、私も癒されます。うちの息子は1歳のころから既に私に腕枕をしてくれてました(私を抱き寄せようとしてのことですが)。添い寝をしないのは多分に親の都合だと(私は)思っています。それも仕方ないですよね。
育児とはちょっと離れますが、イギリスの階級の話しが以前でていたので、こちらの本も面白かったです。「不機嫌なメアリー・ポピンズ : イギリス小説と映画から読む『階級』」。ナニーの話しもでてくるので子育てと無関係というわけではないです。
いつものことですが、とりとめなく、しかも長いコメントですみません。
April 6th, 2010 at 10:28 pm
ここのところ育児関係の話が多いですね。
女性は子供ができると、こんなに関心が変わるんですね。
自分には子供も妻もいないですが、少し驚きです。
April 7th, 2010 at 4:13 pm
>mignon1117さん
>私の場合、その頃(息子が生後1ヶ月未満)、全く、育児書を読む余裕(?)すらなかったです。育児書に目を通す時間があるなら、少しでも寝ていたいと思っていたタイプです(汗)。
Tracy HoggとGina Fordの本は出産前に1回目を通していたので、「そういえば、泣き声の聞き分け方が書いてあった!」とか必死で藁にすがる思いで読み返してました(夫も)。
>今年で息子は4歳になりますが、ご紹介されたTracy Hoggのしつけ編、おしゃべり編は、しっくりきています。
私もTracy Hoggは今のとこ気に入ってます。 それにしても、山あり谷ありで、昨日はgrumpy babyでしたが、今日はhappy babyです。
>tanupさん
>yokokloedenさん、立派な育児の大家ですね。(^O^)
いや、全部、本のコピペ&要約です(笑)。
>親(あるいは周囲)がよく微笑みかける赤ちゃんはよく笑うというのをまわりの子どもを見ていて実感します。
私も最近、友達の子ども(9ヵ月)のfacial expressionがあまりにも友達に似ているので驚きました。 心しようと思います。 親がhappyでいることは大事だと思います。
本のご紹介もありがとうございます!
April 7th, 2010 at 6:41 pm
いま日本人ママさん飛行士が、スペースシャトルと国際宇宙ステーションで活躍なさってるんですねえ。こうなると世界級どころか、宇宙級ライフスタイルを云々しないといけなくなる時代も遠からず来るのかもしれません!?!
http://sankei.jp.msn.com/culture/books/100404/bks1004040910001-n1.htm
それにしてもbaronさん、子供ができると関心が変るのは女性だけではありませんよ。
独身から結婚して父親になっていくにつれて、男性には男性なりの険しくも充実した大変化が待っているはずですから、お楽しみに。
April 9th, 2010 at 3:52 am
そういえば、男の育児に関してこんなサイトがありますよ。
http://www.toyama-cmt.ac.jp/~kanagawa/father/kosodate.html
April 9th, 2010 at 2:39 pm
tygertygerさん
>いま日本人ママさん飛行士が、スペースシャトルと国際宇宙ステーションで活躍なさってるんですねえ。
知りませんでした。 宇宙飛行士といえば、向井千秋さんのダンナさんの『君についていこう』を思い出します。
>子供ができると関心が変るのは女性だけではありませんよ。
全くその通りです。 夫の変化も楽しみな毎日です。