最近話をした2人の友人の話。 年は10歳違うし、年収もケタが違うのですが、私には2人がダブって見えました。
- 中国人Y(♀、36歳)
北京生まれ北京育ちの中国人。 高校卒業まで北京だったが、大学はイギリスへ(どこか忘れたけどオックスフォードとか英トップ5のどこか)。
大学卒業後は米大手会計事務所に会計士として就職し、ロンドンと香港で働く。
INSEAD(フランス)でMBA取得。 当時、「私はもう中国(大陸)には帰れないし、帰りたくない。 フェアな実力社会で自由な欧米式生活に慣れきっているし、下方婚志向でキャリア女性を好まない中国人と結婚できるわけがない」と断言していたのが印象的。
INSEAD卒業後は、英系投資銀行(香港オフィス)へキャリアチェンジ。 INSEAD同級生のスペイン人J(戦略コンサル、NYオフィス)と香港 – NYの遠距離恋愛開始。
勤務先の投資銀行を説得し5ヵ月後にNYオフィスに転勤成功、1年後にJと結婚。
NYアッパーウェストにある高級アパートに住み、2人の子供を育てながら(フルタイムナニー付)、今なおウォールストリートの(数少なくなった)投資銀行でキャリアの階段を駆け上る。
今年5月の卒業5周年同窓会(→『5年目の同窓会』)には2人の子供をナニーに預け、Jと出席。 私たちのロンドン引っ越し計画に「いいなー、私もロンドン住みたいなー」と言っていた・・・かと思うと、ある米系名門投資銀行(ロンドンオフィス)のヘッドハントを受け、家族と共に1月からロンドン暮らしだと言うメールがつい先日届いた。
- 中国系マレーシア人E(♀、27歳)
生まれも育ちもクアラルンプール(KL)の中国系マレーシア人。 高校卒業までKL、大学はケンブリッジでエンジニアリング専攻。
大学卒業後はロンドンの英系戦略コンサルでアナリストとして就職。 3年働くが、出張の多い生活に疲れ、一昨年、エクイティリサーチファーム(ロンドン)に転職。 ロンドンのド真ん中のフラットをシェアし、平日は株のアナリストとして働きながら(徒歩通勤)、休日は友人とショッピング・外食・ライブハウス通い・・・好きなことを好きな時間に楽しむ生活。
先月ロンドンに行った際に会ったところ「今の自由な生活が大好き。 社会の有言・無言の圧力・規律・慣習などに従わさせられるアジアには戻りたくない」とのこと。
———–
アグレッシブさは全然違うのですが、動機や感覚は似ているなー、この2人。
なお、海外経験のある中国人(中国系)の友人の中には(自分がほとんど住んだことがなくても)オポチュニティーに溢れる中国に戻る人も多く(→『華僑の移住モデル』)、彼女たちのように「もう絶対戻らない」と決めている人たちばかりではありません。
前置き(例)が長くなってしまったけど、この「(英語圏でビザさえあれば)どこでも働いて食べていける」彼女たちを生み出した転機はどこかと言えば、大学でのイギリス留学、大学院ではない(→『海外就職における「日本の力」』の1.のケース)。
元世銀副総裁の西水美恵子さんが、
世界銀行で取りたい人が見つからなくなった。 海外で仕事や大学に行っている日本人であれば世界銀行で取りたい人材がいるが、日本から直接では欲しい人が見つからないようになった(『教育における重要な変化』)。
と嘆き、大前研一さんが、
日本人は、明治以降、戦後20~30年くらいまでは優秀だった。 しかし今や学校は世界のどこに出しても恥ずかしい人間しか作り出さない(『大前研一の辛口ニッポン応援談』)。
と叱咤する。
この現状には日本の初等教育・中等教育それぞれに問題があるのでしょうが、決定的に差がついてしまうのは大学でしょう・・・
私は日本の教育改革論を論じていないので、個人ができることとして(辛うじて)「スムーズに」外の世界に溶け込める段階は大学院留学ではなく大学留学だと、自分や周りの経験から思います(もちろん留学先で切磋琢磨しながら死ぬほど勉強することが前提)。 大学院留学からでも無理ではないけど決して「スムーズに」とはいかず、相当サバイバル型になるかと。 もちろん時計の針は巻き戻せないので、それでも必死で食らいつくという戦略は正しいのですが。
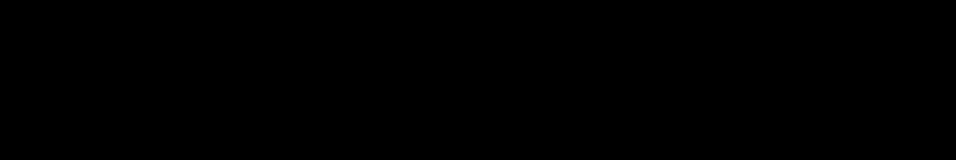

December 21st, 2009 at 6:58 pm
「大学院留学ではなく大学留学」ということでしたが、僕は
「大学留学ではなく大学院留学、もしくは高校留学」
と考えます。ヨーロッパのことは詳しく知らないので、以下アメリカの話です。
あるキャリアパスにスムーズに乗るためには、それなりのアカデミックパスに乗ってないと難しい。
専門によって多少の違いはあるかもしれませが、MBAを例にとると合格判定は以下の4点で行われます。
1)GPA(学部の成績)
2)推薦状
3)エッセイ
4)GMAT得点
つまり学部成績で低くとも3.5以上、平均3.7程度ないと、入学者平均には届かず、合格の可能性が極端に下がります。
高校まで日本で勉強していた学生がいきなりアメリカの大学に入ると、1,2年ほどは英語に慣れるだけで大変で、優秀な成績をキープするのはとても難しいとか考えます。そうすると、自然とGPA平均が低い大学院に応募することになり、学歴社会の労働市場ではその後のキャリアトラックもそれ相応に決まってきます。
ところが、大学院留学においては日本の大学の成績で臨めますので、GPAにおける語学によるハンディはありません。大学院で英語で苦労して成績はいまいちでも、修士が最終過程であれば、その後のキャリアには全くといって影響はないでしょう。
さて、僕は高校から留学しましたが、高校で英語を死ぬほど勉強しても、GPA 3.2 でしたので、大学はいわゆる2nd tier でしたが、大学においては死ぬほど勉強しなくても大学院入学では問題ないGPAでした。
僕の大学院で学んでいた日本人留学生の中で、大学留学組は僕の知る限り見当たらず、自分も含めて高校留学組ばかりでした。
大学で同期だった大学留学組日本人は、インター出身は例外として、全員英語で苦しんでいました。彼らの中で修士に上ってきた人も知り合いにはいません。ところが高校留学組はほとんど修士に上がってきました。
アカデミックパスにおいてどの時点で英語の負荷を受け止め、それによるパフォーマンスの低下を受け入れるのかは、特に学歴が重要なキャリアパスを希望される方にはとても重要なことだと考えます。その点で今回は興味深いポストでした
December 21st, 2009 at 8:23 pm
クローデンさん
久しぶりにコメントさせて頂きます。この度のテーマも興味深く読ませて頂きました。私には二人の子どもがいて、その子ども達が大きくなったときの日本にそれほど明るい未来が待っているとは思えないので、子ども達には留学して欲しいなと思っています。やはり気になるのは費用と語学の面でした。
15才からのボーディングスクールで、ELSのある学校は思いの外少ない上、留学経験者にブログコメントを通して聞いてみると、英語をマスターするのにあっぷあっぷで、テンズスクールなどをねらうにはkojiさんが指摘されているようにGPAが厳しくなってしまうようです。また、ボーディングスクールでは年間2-3万ドルは必要で、インターナショナルスチューデントには奨学金は支給しない学校がほとんどでこの点も私にとっては高いハードルとなっています。
また大学からであっても語学の面が厳しいのは変わらない。奨学金に関してはハーバードなどは国籍に関係なく受給できるチャンスはあるようです。
ただ、いずれにしても文系ではネイティブ並に英語をマスターしていないと苦労しそうですね。そこで、国内のインターナショナルスクールに通いながら海外の大学をねらうか、理系にねらいを絞って大学院から留学するのがいいかな?と思っています。もちろん子ども達が希望すればですが・・・
理系の大学院であれば授業料は無料で、さらにチューターなどをすれば小遣い程度の給料をもらうことも可能なのも魅力です。また、理系であれば使われる英語は意外と簡単だと指摘される方もいます。
http://phd.blog50.fc2.com/
いずれにしても、自分の子どもに限らず、日本人にはどんどん海外を目指して欲しいと真に願います。
December 22nd, 2009 at 2:59 am
こんばんは。いつも更新を楽しみ・・・というか励みにしている国内の大学4年生(理系)です。
一年ほどインドにいたのですが、インドでは大学は国内で大学院から留学するのが成功と考える人が(エンジニアでは)多いです。ほとんどのインド人には英米の大学の授業料を払えない、という現実的理由もありますが、大学では英語での授業がほとんどで、(特に理系は)大学院からでも外の世界へスムーズへ移行できるようです。IITsブランドや人脈に対する自信も背景にありそうです。
ただ、これは日本の大学には当てはまらないので、やはり学部からでしょうか。
僕の経験から判断すると、日本の大学教育はむごいです。自分の勉強不足を棚に上げてはいけないのですが、あれに年100万以上出してもらったなんて親に申し訳ない・・・。僕は既に「時計の針は巻き戻せない」組なので必死にサバイバルする予定で準備をしていますが、大学進学時に言われた「留学は大学入試からの逃げ」なんて言葉を真に受けなければ良かったと今更後悔。
一方で学部から留学した人を見ていると、エージェントに頼り過ぎて、実力以下の大学に送り込まれて苦労するということもあるようです。
インドの話ですが、slumdog millionaireは面白かったですね。僕は小説版は少し苦手なんですが、映画版は監督が得意な疾走感が急成長するインドの荒波とそこに生きる主人公たちにマッチして、大満足でした。
そして、GHAJINIとMomentoの繋がりに気付いた日本人がいたことにびっくり!両方とも日本では有名でないので、そんなこと考えるのは自分だけと思ってました。結局、「パクリは嫌!」と思ってGHAJINI本編は見なかったのですが(;^_^A。
“la vie en rose”や”‘la dolce vita’の由来”といったほのぼのするエントリーも好きです。
ロンドン編も楽しみにしています。
December 22nd, 2009 at 9:21 am
>Kojiさん
>「大学院留学ではなく大学留学」ということでしたが、僕は
>「大学留学ではなく大学院留学、もしくは高校留学」
>と考えます。
ありがとうございます。 ややこしい書き方をしているので、わかりにくかったと思いますが、私が大学院留学組なので今まで大学院留学後の海外でのキャリアを書いているつもりですが、「いや、本音を言うと大学院からってのはかなりサバイバル型になってしまうので、大学からの方がいい」っていうエントリーです。
現地に溶け込むのであれば、それは早ければ早い方がいいです。 高校留学ってのは私の周りに(帰国子女でたまたま高校時代に親が駐在だった人を除くと)いないので、対象にしていませんでした。 貴重な体験談をありがとうございます。
>大学院で英語で苦労して成績はいまいちでも、修士が最終過程であれば、その後のキャリアには全くといって影響はないでしょう。
これには私の意見は正反対です。 日本の教育を受けてきてMBAで初めて留学する人のほとんどは日本に帰ります(今年はHBSですら日本人でアメリカに残れた人はゼロだと聞きました)。 理由はこちらに書いてます(→ http://www.ladolcevita.jp/blog/global/2009/04/post-171.php )が、英語以前の文化的な側面(クラスでわからないことは何でもみんなの前で手をあげて聞いてしまう、ディスカッションしながらチームでテキパキと物事を決めていく)についていけず、MBAの授業より100倍大変な実際のその後のキャリア現場で通用するわけがありません。 おまけにMBAの年になると年齢的にリスクを取れないと考えてしまう人も多いです(私は短期的なリスクは長期的にはチャンスだと思っていますが)。
文化的な側面から慣れるためには、それは早ければ早い方がいいと思いますが、高校から留学するためには本人の意思より親の意向が強いと思うので、誰もが取れる手段ではないですねー。
>hideさん
最近はボーディングスクールやインターに入れたい親御さんが多いんですねー。 シンガポールでも両親とも日本人だけど、子供の教育はずっとインターで英語で、という方を何組か知ってます。
>やはり気になるのは費用と語学の面でした。
英語については、私は日本にいてできる限り最大のことを留学前にするしかないと思っています。 私自身「日本人として日本で勉強できるのはこれが限界」というところまでして行きました。 他のアジア人と比べてハンディキャップは変わらないと思うのに、日本人は勝手に「現地に行かなければマスターできない」「現地にいればできる」と思っている人が多すぎると思います。 お子さんの動機付けというのはこれまた大変だと思いますが。
費用については確かに頭が痛いですが、子供の教育に限りなくお金がかかるようになってきているのは、大都市共通だと思います(→ http://www.ladolcevita.jp/blog/global/2009/08/post-250.php )。
私はロンドンのことしか調べていませんが、公立小学校間のレベル差が激しく、入学年齢前の子供を持つ親が人気のある公立小学校の周りに引っ越したがるため家賃が高騰しています(→ http://www.ladolcevita.jp/blog/global/2009/12/post-290.php )。 家賃差はそのまま治安の差になるので、高くても治安を考えると住まざるを得ない状況です。 公立小学校でこれなので、私立や中学以降は推して知るべし・・・
教育にかかるお金がどんどん膨れ上がっているという現状は払える人が世の中にいる以上解決しそうな問題ではなく、私にも解がありません・・・
>理系にねらいを絞って大学院から留学するのがいいかな?と思っています。
これはインド人と中国人が大得意の戦略で、これからもどんどん欧米トップスクールの学歴を持った理系インド人・中国人が量産されると思うので、すごく苦労しても「フツーのエンジニア」になってしまう可能性がありますね。 「フツーの文系」と「フツーのエンジニア」、どっちがいいかといえば、自分がやってて楽しい方、好きな方がいいと思うので、「留学が簡単」「英語が簡単」というだけが理由であれば本末転倒だと思います。
私自身、「女は文系」「語学ができるから文系」という変な社会的固定観念がなければ理系にいってたかもなー、と思うのでうらやましくもありますが。
December 22nd, 2009 at 9:36 am
>ゆうさん
インドとはこれまたホットな場所にいらっしゃったんですね。
>大学では英語での授業がほとんどで、(特に理系は)大学院からでも外の世界へスムーズへ移行できるようです。
上の方が書いてますが、英語の壁が大きいでしょうね。 エントリーでは高校まで英語教育じゃなかった人を選んで「でも大学から乗ると大丈夫」という意味で書きました(あ、マレーシアは英語教育もあるかも)。
>大学進学時に言われた「留学は大学入試からの逃げ」なんて言葉を真に受けなければ良かったと今更後悔。
今でもそんなこと言われるんですか?(「東大よりハーバードに行こう!?」という本が出る時代なのに、読んでないけど) 私は高校は大阪の進学校でしたが留学しようなんて人は皆無でしたし、親の反対を押し切るだけの確信もありませんでした。 このブログを読んでいるほとんどの人は(書いてる私も含め)「時計の針は巻き戻せない」組なので(・・・と思いつつ書いた)、がんばりましょう!
>GHAJINIとMomentoの繋がりに気付いた日本人がいたことにびっくり!
ネタバラしすると気づいたのは私ではなく夫です。 GHAJINIは全然どんなストーリーか知らずにインドで見た(ヒンズー語で)のですが、暴力シーンが多くてダメでした。 Slumdog Millionaireはよかったけど。
これからもぜひコメントしてください〜
December 23rd, 2009 at 2:03 pm
ずいぶんと昔の話ですけど、都立の高3から米東海岸の高3になって、英語にはえらく苦労しました。
州立の大学にすんなり入りましたが、それもSATの数学テストが都立の入試よりやさしかったのでほぼ満点取れたおかげで、英語テストのほうは限りなく最低点に近かったです。
大学の初めてのアドバイザーから「理系専攻でしょ?」と聞かれたので「いえ、文学をやりたい」と言ったら、顎でも外れそうな顔でびっくりされましたね。あの時点で心を入れ替えて、理系に進むべきであったかも。
院での奨学金欲しさにDean’s Listで通して、無事バカセに到りましたが、一番苦労し、また勉強になったのは英文エッセイの書き方でした。私はあれだけ苦労したのに、娘の例を見ていたら、小学校の高学年から始めて高校1,2年までにはちゃんと出来上がっていたのにはギャフンとしました。だからでもないけど、文系なら大学から、理系なら院からでもいいのかなと思います。
シンガポールは伯父の代から関係があり、南洋、SMU、NUSと知人もいるので懐かしく思い、お便りさせていただきました。ロンドンでもどうぞご活躍ください。
キャリアもさることながら、次の一大チャレンジは子育てかもしれませんね。
December 24th, 2009 at 1:10 pm
>tigertigerさん
>院での奨学金欲しさにDean’s Listで通して、無事バカセに到りましたが、一番苦労し、また勉強になったのは英文エッセイの書き方でした。
Dean’s Listはすごい! 英文エッセイの書き方はみっちり鍛えられたいですねー、それは大学院では遅いかも。 今でも自信ありません。
>娘の例を見ていたら、小学校の高学年から始めて高校1,2年までにはちゃんと出来上がっていたのにはギャフンとしました。
日本でですか? アメリカで? 子供のバイリンガル教育は本当に悩むことになると思います。 誰かバイリンガル教育のauthorityとかいるのでしょうか?
January 1st, 2010 at 2:52 pm
これは西海岸のGifted Program校での例ですが、多分全米の進んだ学校教育ならどこにでもあてはまるでしょう。私は少し早トチリ的に「二兎を追ってもモノにならんとマズイ」と考えてしまったものですから、英語教育だけで通してしまったので、バイリンガル教育に関しては残念ながらよく知りません。
こちらの大学で日本文学を教えていた頃、あまりに沢山のアメリカ人の学生がちゃんとした文章が書けない事にビックリしたことと、たまたま知っていたバイリンガルの学生が読みが苦手で、「坊ちゃん」の数ページを読むのに一大苦労をしていたのが印象に残ってしまっていたおかげです。
アメリカでバイリンガルに育てるためには、土曜日に補修校に行かないと行けないのですが、これは親がよほどガンとしていないとやり通せません。うちの娘は、小学生の頃「土曜にも学校行って日本語習うか?」と聞かれたときには当然「NO」と答えていたくせに、大学生になってから「やっぱり補修校に行ってたら苦労しないでバイリンガルになれたかも」などと言い出しました。
しかしながら苦労しないでなれるはずは到底なく、周囲の成功例を見てみますと、家庭内で子供と母親は主に日本語しか使わず、そしてそれを許容する物分りの良い配偶者に恵まれ、かつ休みごとに頻繁に日本に里帰りすることの可能な余裕のある環境要素などが必須といってよいようです。
それからカニングハム 久子著「海外子女教育事情」(新潮選書) は、1988年出版で古めいてしまっていそうでちっとも古くなっていない怖い本です。
January 4th, 2010 at 9:52 am
>tygertygerさん
詳しくありがとうございます。
>私は少し早トチリ的に「二兎を追ってもモノにならんとマズイ」と考えてしまったものですから、英語教育だけで通してしまったので
私もそう思っていました。 でも子供ができた友達が全員バイリンガル教育に挑戦しているので(日・英に限らず、中・英などいろいろ)、私が勝手に決めてしまうのもどうかなー、と考えを改めたところです。
>アメリカでバイリンガルに育てるためには、土曜日に補修校に行かないと行けないのですが、これは親がよほどガンとしていないとやり通せません。
>家庭内で子供と母親は主に日本語しか使わず、そしてそれを許容する物分りの良い配偶者に恵まれ、かつ休みごとに頻繁に日本に里帰りすることの可能な余裕のある環境要素などが必須
私が情報収集したところによると、アメリカに限らずどこで育てても全くおっしゃる通りのようです。
上記のように育てられて日英バイリンガルになったものの「小学校の頃から(補修校の)勉強ばかりで遊んだ記憶がないから、自分の子供は遊ばせたい」という人もいますし、子供を休みごとに日本に里帰りさせて短期間スクールに入れつつ「日本人並みに漢字の読み書きができるところまでは求めてない」という人もいます。
自分の経験や子供の性格にもよるのでしょうし、ケース・バイ・ケースですねー・・・ 本のご紹介もありがとうございます。 1988年出版とは・・・
April 14th, 2010 at 1:32 pm
『大前 研一 実践英語』ボリューム映像詰め合わせ
大前 研一 のビジネス・ブレークスルー大学院大学より、 「 ビジネス実践英語を、“成功している方”から学びたい 」 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~…