先週のエントリーでmegumeguさんからブログネタのリクエストがあったので、今日は「求職者の心構え」と題し、思うところを書きます(・・・と私がちんたら考えている間に、megumeguさんは採用内定されました。 おめでとうございます!)。
[ 初めにお断り ]
私は日本で2回転職していますが、2回とも人材紹介会社に登録したらすぐ紹介され面接を受けたらすぐ決まったという、余り参考にならない体験をしているので、下に書くことはどちらかというと去年から今年にかけてシンガポールで職を求める中で感じてきたこと、及び周りのケースを見てきた上での総括です。
私としては普遍的なことだと思っているので「日本では参考にならない」とか決め付けずにお読みください。
また人材業界のプロでもなんでもないので履歴書の書き方、面接の心構えなどは他のもっとふさわしい人に聞いてください。
1. 巷に出ている求人だけが企業の人材需要ではない
企業のウェブサイト・人材紹介会社・ヘッドハンター・・・etc.に出ているだけが企業の人材需要ではありません。
「こういう人が欲しいんだけど社内で探そうか、どうしようか?」という顕在化する前の需要、人材が必要ということさえ明確に認識されていない潜在需要。 人材紹介会社はフィーが高いしリスクもあるので採用は信頼する人の紹介に頼るという会社、求職者の熱意に押されて予定していなかったポジションをつくる会社・・・ 世の中にはこんなケースが溢れています。
私が知っているケース(イタリア人ですが)。 フェラーリにどうしても勤めたくて、ほとんど求人も出ないので毎日工場に通い始めます、アポなしでふら〜っと。 毎日通うので工員たちと仲良くなり、自分がやりたいことを話しているうちにそのうちオフィス内にも入れるようになり、初めは小さいアルバイトをもらい、最終的には正社員になって自分がやりたいと思っていた仕事についてしまった、というもの。
このケースは極端ですが、巷に出ている求人以外の職を掘り起こそうと思ったら、とにかく人的ネットワークが必要です。
転職のような人生の重大事に有用な情報は、身近な強いネットワーク(親しい友人)ではなく、遠くの緩いネットワーク(遠い知人)から得られるという理論もあります(なので親兄弟や親友ではなく、しばらく会ってない学生時代の友人や社外で知り合った人に求職中であること、望む職の内容を話しましょう)。
この方法の欠点は時間がかかることですが、この点は仕方ありません。 私のシンガポール就職活動も未曾有の金融危機の最中、ネットワーク構築から始め(→『人は意外と会ってくれる』)、この時会った人に半年後くらいにまた別の人に紹介されて今の仕事が決まりました。
2. 人材紹介会社やヘッドハンターの言うことを鵜呑みにしない
結構何人もの友人から「いいヘッドハンターに出会えない」という声を聞きます。 ヘッドハンターには年齢を理由に紹介さえ渋られた案件に、自分で直接アプローチしたら採用された、という事例さえあります。 彼らは現在の人材市場の需給動向など「市場」の情報を知るのには良いソースですが、必ずしも良い「転職アドバイス」をくれるとは限りません。
彼らのインセンティブの源泉を見ると明らかですが、多くの人材紹介会社は採用企業と求職者が合意しディールが成立して初めて成功報酬を得られるというフィー体系になっています(エゴンゼンダーなどトップのヘッドハンターは異なる)。 担当者個人の報酬も成功報酬にある程度リンクしていることが多いです。 どうしても「ディールを成立させる」ことが目的となってしまうため、求人内容と職務経験をマッチングさせるのは上手ですが、求職者の過去の経験からポテンシャルを読み解き、思わぬ可能性を花開かせてくれることを期待するのはやめましょう。
間違っても「これからどういうキャリアを築けばいいか」などと聞いてはいけません。 そんなことはおそらく彼らのところに行く前に自分で考えて考え抜くべきことなのだと思います(結果論的に『キャリアドリフト』になってしまっても、それはそれでOK)。
3. 就職活動はパートナー探しと同じ、「縁」であり、「人格や経験の善し悪し」ではない
特にこういう時代は、なかなか結果が出ないこともあり暗くなる一方になりがちですが、「独身者がほとんどいない婚活市場」みたいなもんで、「実力不足、努力不足」などと自分を責める必要は全くありません。
また、複数の人からモテる必要はなく、1人から「噛めば噛むほど味が出る」と思われればいいところも同じ(パートナー探しよりさらに気楽なのは、失敗したってどうってことないってことでしょうか? まあパートナー探しも失敗してもセカンドチャンスとかあるわけですが)
シニアになればなるほど、小さい会社になればなるほど、「会社と合うか、経営者と合うか、上司や同僚と合うか」が大事になってくるので、「数打ちゃ当たる」作戦ではなく、お互いにじっくりと向き合い見極めることが重要になってきます。
最後に、この長い孤独なプロセスを常に励まし前へ向かせてくれる人が近くにいると、やはり心強いです。 私もシンガポールではストレスいっぱいだったので夫がいなければ2ヵ月くらいで日本に逃げ帰ってたと思います(夫がいなければシンガポールに初めから来ていない、という説もあるが)。
焦らず(というのは無理ですが)、じっくりとよい求職活動を♪
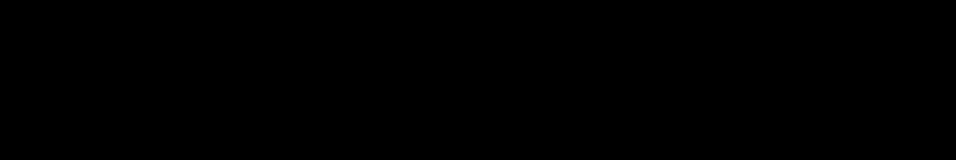

August 13th, 2009 at 1:05 pm
イタリア人のケース、スピルバーグに似ていますね。
2001年超氷河期に就職した者としては
>人的ネットワーク
の必要性を強く感じました。
同じ学年で100社も採用試験を受けたクラスメートがいたのですが、私は友人・知人の紹介で2社から声がかかりました。
もし新卒だったらいろんなバイト経験を積んでおくのもいいかと思います。
August 13th, 2009 at 6:56 pm
la dolce vitaさん、就職の決まったmegumeguさん(おめでとうございます!)、
もしかすると40歳を超えて転職、なんてこのご時世にド阿呆な人間の話は参考にならないかも知れませんが、最近の話でもあり少し乗じて書いてみようかと思います。あくまで私の場合であり、一般化は出来ないという前提です。
まず表に出ない求職ですが、業界によってはアングラなネットワークがあり、そこで決まることもあるそうです。私が聞いたものは半導体製造関係ですが、ただその場合はやはりその業界のスキルが前提になりますので、同じ業界転職することが大前提です。じゃあそうネットワークは何処で分かるのか?と言われれば、関連しているが全く同じで無い、それなりに業界での実績を積んでいる人を当たることでしょうか。物凄い顔、ということではなく、「ああ、あの人ね」と言われる人が業界にはいるはずなので、そういう人と話す、というのはありだと思います。
私の場合、ヘッドハンターからの連絡を貰ったこともありますが、結局は紹介会社からの話で決まりました。正直なところ、最初に話のあったところにポンと決めたという何ともいい加減な話なんですが、一斉に就職活動を行なう新卒とは違い、待てば良いというものでもなく、この辺は縁と勘でしょうか。初めてその会社に行って紹介されて、3回くらい面接と試験があったでしょうか。「まあ『来てくれ』と言ってるんだから、その話に乗ってそう酷いことにはならないだろう」ということでしょうか。ただ、私の場合高校・中学の子供がいることもあり、さすがに失敗は許されないという重圧は相当ありましたし、今でもその重圧はあります。
私の場合は無職の期間を持たない転職で、かなり気を楽に転職活動をしていたと思います。むしろ決まってからの社内での立場の方が辛かったですね。これは針のむしろとかではなく、非常に仲のよかったチームの連中と離れるのが苦しかった、というのがあります。もう一つ、その前年に私自身がヘッドハントして、一人を同じチームに転職させているんですね。会社としての行動であるとはいえ、その点も苦しかったことです。
あと、その後の人的ネットワークを考えると、前職の人たちとの関係は保った方が良いと思います。私の場合は幸いにも、チームや他の部署の先輩・同僚・後輩とも関係が継続していて、何のかんので今でも良く遊んでいます。そこの距離感をどう持つかというのは正直難しいところはありますが、単純に仲のいい人は多い方がいい、という思想です。もしかすると出戻ることだってあり得るわけで、私も「お前さ、2-3年で上手く行かなきゃさ、また戻って来いや。ちゃんとポストは用意しておくからさ」と言ってくれる人がいるので、転職を「会社の変わる人事異動」と捉えられているところはあります。
人的ネットワークというのは、そこで具体的な話がなかったとして、「心のセーフティーネット」になるんですね。逆にそういうネットワークが広がったから転職に踏み切った、というところもあります。
August 13th, 2009 at 11:28 pm
la dolce vitaさん,リクエストに答えてくださってありがとうございます。
ドイツ特派員さんも、おめでとうのお言葉ありがとうございます。
私は世界級では無く、日本の地方級の就職活動で厳しい現実に遭っていました。でも、「住む世界が違う」などと思わずに勇気を出してla dolce vitaさんにリクエストして良かったです。
>就職活動はパートナー探しと同じ、「縁」であり、「人格や経験の善し悪し」ではない
la dolce vitaさんの記事のこの文は本当にありがたいです。
私は、就職試験の面接に落ちると人格を否定されたような気になり、いつも自分を責めていました。また、面接が盛り上がって採用かな?なんて期待しちゃった後の不合格通知は人間不信につながって(あの面接官の笑顔はなんだったの?みたいな)人に会う回数が減ってしまったりします。人格を否定されたわけじゃないんだと気持ちを立て直そうとしても私にはなかなか難しく暗い日々でした。
でも、活字でガツンと
>就職活動はパートナー探しと同じ、「縁」であり、「人格や経験の善し悪し」ではない
と言われると、そうだよな〜と妙に納得して気持ちが明るくなりました。ありがとうございました。
こちらの記事や他の方のコメントや自分の失敗経験を通じて、就職に関しても就職で悩んだ時の心の支えとしても、やはり人的ネットワークって大事だな、と思いました。
私はこの1ヶ月程、地方の限られたマーケットの中のキーパーソンと面接で色々話すことができたので、それは一つの出会いと捉えて、今後関係イベントなどでその方々とお会いした時は「以前面接でお世話になりました〜」って笑って挨拶していくぐらいの心意気でいたいなと思っています。また、今後は意識していろんな人と会う機会を作っていきたいなと思います。
様々なアドバイスありがとうございました。
あと、話逸れますが「京のおばんざいレシピ」ブログ本当に参考になります。私は東北生まれ&在住なんですが、学生時代と少し会社員生活を大阪で過ごしていて、関西風の味付けが大好きなんです!
August 14th, 2009 at 9:42 am
>MyFireさん
>イタリア人のケース、スピルバーグに似ていますね。
あ、そうなの? 知らなかったー
>私は友人・知人の紹介で2社から声がかかりました。
すごいね。 新卒の頃は私、ネットワークとか考えもしなかったなー
>ドイツ特派員さん
経験談ありがとうございます!
>業界によってはアングラなネットワークがあり、そこで決まることもあるそうです。
どこの業界も狭いですよね、コンファレンスとか顔出してると、いつも同じメンツってことはよくあります。 私はあまり特定の業界に自分のキャリアを縛られたくないので、業界内で転職したことはないですが。
>その後の人的ネットワークを考えると、前職の人たちとの関係は保った方が良いと思います。
これは「立つ鳥、跡を濁さず」と共に重要だと思いますが、かなり出身先の会社のキャラによりますねー。 特に同業他社への転職だと口も利いてくれないところはいまだにあると思います。
出戻りが多い会社ってありますよね(私が以前いたS社とか)。 いい会社なんだろうなー、と思います。
>megumeguさん
どういたしまして〜
>私は、就職試験の面接に落ちると人格を否定されたような気になり、いつも自分を責めていました。
本当にへこみますよね。 私も夫にいつも言われてたんですよ、「へこんだ態度が次の面接で出ちゃう」って。
採用されない理由ってほんとさまざまで、「この人には、うちのあのアクの強いAさんと組んでもらうことになるけど優しすぎて折れちゃうんじゃなかろうか?」とか、「この仕事、雑用が多いからこの人にはもったいないな、飽きちゃうだろうな」とか、人格・経験・能力の不足が理由ではないケースが山ほどあります。 ほんと「相性」ですね。
付き合ってから「この人合わない」って気づくよりも、初めから断ってくれた方がいいですよね?
>今後は意識していろんな人と会う機会を作っていきたいなと思います。
私もいつも転職のたびに気づくのでなかなか普段からできていません。 お互いがんばりましょー
>学生時代と少し会社員生活を大阪で過ごしていて、関西風の味付けが大好きなんです!
ありがとうございます♪ 私もすごーく薄い味付けで育ったのですが、なかなか関西風のレシピってないんですよねー 今は親の味付けより随分濃くなってしまったと思います。 あー、お盆だし家に帰りたい〜(笑)