先月、『北海道ベンチャーキャピタル』というエントリーを書いたところ、代表の松田さんは、3月に東京でお会いした外村さんのお知り合いということで、メールで松田さんに紹介して頂きました。
いやー、ブログに書いてみるもんですね。 外村さん、ありがとうございます!
今日はその北海道ベンチャーキャピタルの松田さんから「オープンイノベーションのためのベンチャー投資」というレポートを教えて頂いたので紹介。
「オープンイノベーション」は社内のアイデアに頼るだけでなく、社外のアイデアをも上手く使い、企業の境界線を越えて、研究開発や事業化を進めることで、新たなマーケットを創出するということである(『HVCビジネスレポート:オープン・イノベーションへの期待』より)。
 アメリカやヨーロッパは、過去20年、オープン・イノベーションを進めたが故に、大企業の競争力は増し、ベンチャーにとっても大学にとっても活性化の源泉となっているそうです、三方win-win(右図はオープン・イノベーションによる研究開発のイメージ図)。 一方、日本は内製化にこだわり、外の新しい技術に重点を置いてこなかった、と。
アメリカやヨーロッパは、過去20年、オープン・イノベーションを進めたが故に、大企業の競争力は増し、ベンチャーにとっても大学にとっても活性化の源泉となっているそうです、三方win-win(右図はオープン・イノベーションによる研究開発のイメージ図)。 一方、日本は内製化にこだわり、外の新しい技術に重点を置いてこなかった、と。
私が驚いたのはHVCレポート『欧米企業のオープン・イノベーションへの取組』にあった独化学品大手BASFや米製薬大手Merckの例。 研究開発が生命線の製薬業界、最近また大型買収が続き再編の動きが加速していますが、Merckは外部の技術を取り入れることにも非常にどん欲です。
技術スカウトをグローバルに配置し、社外ネットワークを築く一方、ウェブサイト上で同社が必要としている開発テーマ、技術のシードというトップ・シークレットを公開することにより、確実に必要なパートナーを効率よく見つけようとしている意図が伺えます。
ひと昔であれば、競争力の源泉である研究開発は社内に囲い込むのが企業戦略上重要だったと思うのですが、世界のトップ製薬企業ではとっくにそうではなくなっているのですね。
こちらで紹介した『イノベーションのジレンマ』では、企業がイノベーションのジレンマを克服するためには、大企業が破壊的テクノロジー開発による数々のジレンマ(既存テクノロジーとカニバる、高いオーバーヘッドをカバーできない、etc.)を避けるために、完全に自立した子会社をつくるというのがひとつの解でした。 外部の力を内部に取り入れるオープンイノベーションではベンチャーや大学が大企業の「社外研究開発機関」になっていて、イノベーションのジレンマを克服しているんでしょうか?
すると、以前まではインターネット業界では成功エグジットプランが「IPOすること」だったのが、ここ最近「Googleに買収されること」になったと言われているように、他の業界でも「大企業に買収されること」がエグジットプランになるんだろうか?、などいろいろ考えてしまいます。
また、製品開発に社外の知恵を借りるのは、製薬業界に限らず、米PCメーカーのDellがIdea Stormというサイトで製品へのユーザーの要望を吸い上げたり、StarbucksがMy Starbucks Ideaというサイトで商品やサービスのアイデアを募ったりしています。
こちらはどちらかというとこのエントリーに書いた「群衆の叡智」をいかした顧客サービスに近いですが。
こういう傾向が続くと「企業の競争力の源泉って何だろう?」というものすごく根本的な疑問に当たってしまいました。
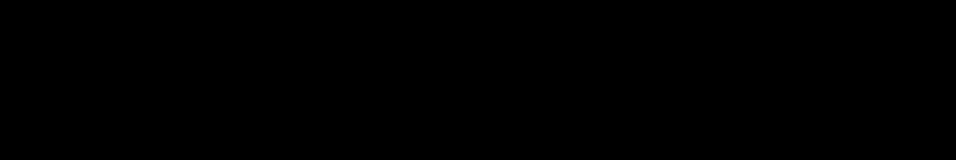

June 18th, 2009 at 7:13 pm
la dolce vitaさん、
私が知っている(実際に経験した)中で一番びっくりしたのはIBM。あのワトソン研を擁して、世界一の特許数を誇るIBMが、半導体開発では既にAlbany大学へ委託をしています。
http://www.azonano.com/news.asp?newsID=10654
ではAlbany大学が全部やっているのか?と言われればこれはこれでまた更に他大学と連携、研究内容の得意不得意で更にその外の大学に研究を振り分けるんだそうです。
更に言えばこのAlbany、この地を「東のシリコンバレーにする」という目的の元、Sematechという半導体研究機関をTexasからごっそり買収してしまいました。
http://www.solid-state.com/articles/article_display.html?id=292297
では何故こんなことをするのか?大きな原因はIBMに限らず、半導体という分野の開発投資が巨額になっていること。何しろ試験設備だけでン十億で、工場一つが最低2000億円程度掛かります。これに掛かる開発も半端ではなく、それを金銭的に単独で出来るのは今やIntel・Samsung・TSMCという三社だけでしょう。IBMだってハード分野の損益は悪い上、何しろ波の激しいことに加えて時間が掛かる研究開発が多く、こうやって資源分散をする、ということでしょうね。BASFやMerckにしても、製薬開発はかなり時間が掛かりますから、自社で抱え込む難しさは益々増えるんじゃないでしょうか?囲い込むメリットよりも、金と時間を掛けるデメリットの方が大きくなっているということかな?と思います。
AlbanyはAlbanyで、ちゃんと開発の仕事を持ってくる業界通の渉外担当を置いていて、その人が開発に関わる仕事を持ってくるわけです。例えばこんな人。営業担当ですね(おもろいおっさんです)。
http://cnse.albany.edu/News/index.cfm?step=show_detail&NewsID=984
恐らくここで問題になるのは、IPの取り扱い。共同開発の成果を何処にどう帰属させるか、ということの引っ張り合いがあるはずです。何故なら、ここがAlbanyとIBMだけのものなら簡単ですが、そこに付随する色々な会社が入っているため、二つに分ける、というだけではないところが残るから。
IPOではなく企業売却が目的、ということでは、既にCISCOなどが先鞭をつけているようなことですね。実際にCISCOには「ベンチャー買います窓口」みたいなものがHP上にあり、そこにベンチャーが売却を売り込むんだそうです。
私個人は、企業の競争力の源泉は「人」だと思っていますが、そういう定性的ではない何か、が難しいですね。トヨタにあってGMにないもの、GEにあって日立にないもの、何なんでしょうねえ?
June 19th, 2009 at 9:45 am
>ドイツ特派員さん
ありがとうございます。
IBM、Albanyの件は知りませんでしたが、本気ですね(当たり前か・・・)。
>囲い込むメリットよりも、金と時間を掛けるデメリットの方が大きくなっているということかな?と思います。
おっしゃるとおりだと思います。
>IPOではなく企業売却が目的、ということでは、既にCISCOなどが先鞭をつけているようなことですね。
ベンチャーのExitが大企業への売却になると、小さい会社か巨大会社しか残らず、真ん中が全部淘汰されるか買収されることになると思うんですよ(いわゆる二極化)。 もちろん独禁法とかあるんですが、超巨大企業しか残らない世の中って怖いな、と思ったりもする。
>私個人は、企業の競争力の源泉は「人」だと思っていますが、そういう定性的ではない何か、が難しいですね。
「人」なんでしょうが、カリフォルニアのように1社への平均在籍期間が2年というような場所では「人」は常に流動的なのです。 すると、「必要な人を必要なときにすばやく集める力」が競争力になるんでしょうか? なんか違う気がするんだけどなー・・・
June 21st, 2009 at 10:42 am
la dolce vita さま
はじめまして、長野県の北八ヶ岳を眺めながら、「スローなユビキタスライフ」を楽しんでいるM-SAKUネットさんです。
「企業イノベーション」について、Googleしていましたら、このページに偶然たどりつきました。
そして、「世界級ライフスタイル」という題名に目を魅かれ、ABOUTとその背景を熟読させて頂きました。
ワー、すごいなー! 田舎でのんびり過ごしながら時々東京に出かけていくライフスタイルの自分からは、考えられない世界中で過ごされている方々が多いことに感心しながら、「オープンイノベーション時代の企業のあり方」を何度も読まさせて頂きました。
>こういう傾向が続くと「企業の競争力の源泉って何だろう?」というものすごく根本的な疑問に当たってしまいました。
私もそう感じました。
そして、このような環境をうまく利活用すると、もしかしたら、個人でもネット的な企業になりうるのではないか、という感覚すらおぼえるようになってまいりました。
そんなことができたら、それが「世界級ライフスタイルのひとつ」になるかもしれませんね。
もしかしたら、「オープンイノベーション時代の企業のあり方」ではなくて、「オープンイノベーション時代の個人のあり方」が問われているのかもしれませんね。
こんなあんなことを想像する機会を与えて頂いて、ありがとうございました。
June 21st, 2009 at 11:23 am
>M-SAKUネットさん
はじめまして!
>もしかしたら、個人でもネット的な企業になりうるのではないか、という感覚すらおぼえるようになってまいりました。
全くおっしゃるとおりで、最近『企業の競争相手が個人になる時代』というエントリーも書きました。
http://www.ladolcevita.jp/blog/global/2009/06/post-204.php
私は「地方にいながらにして世界最高峰の知やツールにアクセスできる時代になった」と感慨を覚えていたのですが、一方で世界最高峰の知やツールがネット上に溢れていることを知っている人は実は東京に集中していたりすることにも気づき、どうしたもんかなー?と思案していたところでした。
八ヶ岳を眺めながら世界に向けたサービスを提供する、なんて素敵だと思います。
June 21st, 2009 at 9:55 pm
la dolce vitaさん、
いやあ長野からでも直ぐにアクセスできるというこのインターネットという道具、上手く使わない手はないですね。実は去年まで私は長野に約8年単身赴任の形を取っていました。
で、この企業の競争力の源泉について、まだ纏まりませんね。ちょっと整理のために利用させていただいているところもあるので、ご容赦下さい(笑)。
確かにカリフォルニア辺りの労働流動は激しいんだと思いますが、そのアメリカでも、製造業の勤続年数って結構長いんじゃないかな?と思っています。例えば前職で8年程同じ業界で仕事していましたが、アメリカの会社での担当者はほとんど変わらなかったし、変わってもあくまで社内異動という場合が多かった気がします。意外と生え抜きが頑張る会社が多いという印象です。この辺の統計的なものってあるんでしょうか(サボって調べていません)。
実は日本の開発が囲い込めたのは、この労働流動性の低さがあったのかもしれません。長期に渡って利益が直ぐに出ない仕事をさせることができるのは、日本的労働流動性の低いところには好都合だったんじゃないでしょうか。ところが、どんどん開発期間が短くなってくると、むしろその短い時間にどれだけ集中した人員を掛けられるか、どれだけ最新の技術を持った人員を持ってくるか、ということに変化してきた可能性がありますね(la dolce vitaさんが指摘された部分です)。ただ、それだけが企業の強さか、と言われると確かにどうなのかな?という疑問は出ますし、そもそも「強い企業」っていうのはどういうものか?というのも実は曖昧だったりします。例えば財務的に強い企業とシェアの高い企業はどちらがいいのか?もっと言えば働く側としての幸福と会社の損益は一致するのか?とか色々な疑問が出ます。例えば、欧州系の企業の一つの指標に「従業員数が大きい」というのがあります。これは、「それだけ世の中に雇用機会を与える企業」という評価になっていて、多少損益性が低くても尊敬される傾向があります。
じゃあこういうオープン開発は企業の強さとどう関連付けられるの?ということをもう少し考えてみたいと思います。今後自身の生活にどう活用するかということも含めてですね。