はやいもので、今日は200エントリー目になりました。 いつも読んで頂いてありがとうございます。
100エントリー目にやったので、今日も記念っぽいエントリーを(そのうちネタ切れしそうですが・・・)。
最近、心がけていることに「’食わず嫌い’と’食った嫌い’を直す」というのがあります。
食べ物の話ではなく、もっと広い意味で(食べ物でも最近ようやく牡蠣嫌いを克服しました、やったー!)。
‘食わず嫌い’の定義を「味覚以外の感覚を通して得た情報を元にネガティブな判断を下してしまい、味わうという経験をする前に嫌ってしまうこと」だとすると、ここで比喩的に用いているのは「経験する前に嫌ってしまうこと」の意。
最近、中国という’食わず嫌い’(というほど強いものではなく、心理的に遠い国、’食わず苦手’くらいだったけど)を克服しました(旅日記→1, 2, 3, 4, 5, 6)。 その心理的な遠さは、メディア情報で形成されるイメージや母の中国人嫌い(本人の個人的な経験からきているので、後で言う’食った嫌い’というやつ)に影響されていたもので、個人的な体験からくるものではなかったので行ってよかったです。
そして、’食わず嫌い’よりもっとやっかいなのが’食った嫌い’。 これは、「個人的な体験を元に嫌いになってしまうこと」を指します。 一応「食ってみた」という体験があるため、一度身につけてしまった先入観を自ら破るのは至難の業。
私が20代後半で克服した’食った嫌い’が「アメリカ人」です。
私は26、27歳の時、当時勤めていた某エレクトロニクス企業の某製品の北米市場開拓というミッションを遂行していたのですが、当時はこの業界の黎明期。 「市場開拓」といえども市場そのものがない時代(もちろん市場調査レポートも売っていない)。 よって、顧客候補、パートナー候補になりそうな人を探し出して会って、「こういう技術があるんですが、どうお役に立てますでしょうか?」みたいな非常にあいまいな御用聞きをし、将来の需要を形作っていくのが役割でした。 ところが、こういう目的も責任もはっきりしない企業同士の技術すり合わせ(下記参考)は日本企業同士の場合うまくいくのですが、相手はアメリカの、しかも米国(国内)事業担当。 ベンダーというのは、既に出来上がったソリューションを提案するのが仕事だと思っている人たち。
誰でも知っているブランドだったため、会ってくれるには会ってくれるのですが、”So? What do you want? Come back in 2 years.(で、結局何なんだっけ? 2年後くらいに(商業的に使えるものにしてから)また来てよ)”と言われる毎日(ここまで直接的な言い方をする人はさすがに少数だったが)。
「擦り合わせ型」のプロセスとは,複数の機能が複数の部品・要素と相互に依存し合う複雑な対応関係になっている製品を開発するために,各部品・要素間を相互に調整し,試行錯誤を繰り返しながら徐々に製品の完成度を上げていくプロセスである(Tech On : 製造業のプロセスはモジュラー型が基本なのか)。
米国ドメドメ企業でおそらく国外に出たこともなく当然日本の事も知らず興味もなく、ミーティングには山のようなクッキーやドーナッツが出て、ぶくぶく太っていて、9/11直後で過剰にピリピリしていて保守的な雰囲気が張りつめていて、おおざっぱで無神経で、声がデカくて・・・
私は徐々に「アメリカ人嫌い」になってしまい、その頃は同僚にもかなり毒を吐いていました(ごめんなさいねー、当時の私を知っている人たち)。 立派な’食った嫌い’のできあがり。
MBAを目指していたものの「絶対アメリカには行くまい」と思っていたし、実際アメリカのビジネススクールは一校も受けませんでした。
そんな私のアメリカ人嫌いを治してくれたのは、INSEADで出会ったアメリカ人。 とりわけ、同じ家をシェアしたアメリカ人A。
世界中から学生が集まるINSEADでも数の上ではヨーロッパ人が多いのですが、非常に一般化して言うと(もちろん個人差は大きい、そしてひと言でヨーロッパと言えど北と南では大違い)、ヨーロッパ人よりアメリカ人の方がpolitically correct( = 言葉・表現が差別的でない、偏見のない)です。 よっぽどアメリカでは意識せざるをえないのでしょうねえ。 表層的な側面だけではなく、きちんと概念として染み渡っている気がしました。
あと、裏表がないのでわかりやすい、「この人、本当に言ってることを思ってるんだろうか?」など勘ぐらなくて済む。
アメリカ人のいいところもたくさん発見し、INSEADが終わる頃には’食った嫌い’もだいぶ治っていました。 「仕事以外で行くことはあるまい」と思ったアメリカに2005年には旅行で行っちゃったし。
ちゃんと違う側面を新たに認識することによって、’食った嫌い’ も治すことができる、ということを発見しました。 Generalization(一般化)は危険で、ちゃんと個人として向き合うべきだ、とも思ったし。
また、人間に好みがあるのは当然なので、ひょんなきっけで何かを嫌いになってしまったとき、少なくとも周りにまき散らさないことは大事かな、と思います。
そしてたとえ’食った嫌い’になってしまっても、それを覆すような新しい情報に出会ったとき、きちんと再評価できるかどうかが自分の頭が錆びていないかどうかのバロメーターになるとも思います。
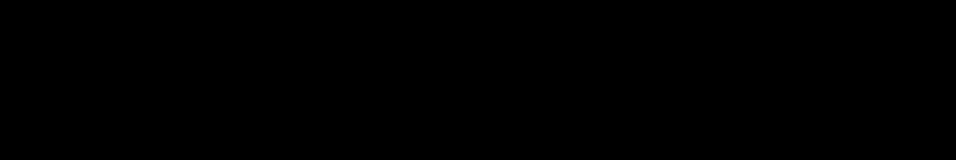

February 17th, 2009 at 10:07 am
アメリカ人はもちろんいろいろいるのは当たり前だから例外があるのは前提としても、アメリカしか知らないようなアメリカ人ってやっぱり前述のアメリカ人像に近いよね。「お友達にはなれない」っていうか・・・。そういうアメリカ人は田舎に行けば行くほど多くなるような気がする。アメリカって国土のほとんどが田舎だからね。だからそういうアメリカ人のほうがアメリカには多いのではと思っています。それに対して、都会にいたり、移民色が強いアメリカ人、国外にいるアメリカ人は「お友達になれそうな人」がたくさんいると経験から思いました。世界はアメリカだけじゃないことを知っているっていうか・・・・。アメリカナンバーワンって思っていないというか・・・。
February 18th, 2009 at 12:38 pm
>ジジ
>アメリカって国土のほとんどが田舎だからね。だからそういうアメリカ人のほうがアメリカには多いのではと思っています。
オバマはケネディ以来の都会出身の大統領だしね。
>世界はアメリカだけじゃないことを知っているっていうか・・・・。アメリカナンバーワンって思っていないというか・・・。
こんな人、アメリカにはいっぱいいるんだけど、実は日本にもいっぱいいるんだよね(苦笑)。