時間が経ってしまったのですが、『チャイナ・ドリーム』と『”泣かせる”夢を持つ人、持たない人』のエントリーを読み、ブログの中でお勧めしたNHKスペシャル『インドの衝撃』を観た任宜(にんぎ)さん(中国人で現在コンサルファームにお勤め)から感想として以下のようなメールを頂きました。
中国やインドの人々は非常に努力をしています。 それは非常にすばらしいし、日本のぬるい大学環境よりもずっと共感できます。
ただ、その源泉が「貧困からの脱出」「現在恵まれている人に追いつき、追い抜くこと」であり、そのパラダイムが彼らの力の源になっています。 それでは本質的に「家族」、「地域」、「国」という枠を抜け出すことはできません。 どこまでいっても「自分と自分の所属するコミュニティ」の向上に終止してしまいます。
それも悪くは決してないのですが、もう一つ目線を上げれるといいなと強く思います。 競争をして勝とうとすることが生物の性ですが、、、、、、
孔子の言葉に「衣食足りて礼節を知る」という言葉があります。 マズローの欲求五段階説じゃありませんが、ある程度満たされた人でないと、本当の意味で世界をリードするというのは難しいのかなと思います。
エネルギーをできるだけ節約することが生物の本能ではあるのですが、お腹一杯の先進国の恵まれたエリート諸兄には、是非世界とはどうあるべきかに思いを馳せてほしいと思います。
そして、
(先進国の)恵まれている人にしかできないことがあり、それに向かって本気で努力する者がいてもいいのではないか。 もし、そういう人に会ったことがあったら教えてほしい
とのことでした。
全くその通りだな、と思いました。
『”泣かせる”夢を持つ人、持たない人』の中に書いた『”泣かせる”夢』とは結局、国・故郷のため・・・という域を出ていないですものね。
そこでリクエストに沿った人を「何らかの社会問題を解決することを最優先目標としている組織体でフルタイムで働いている人」と定義し、周りを見渡してみたのですが、うーん、すぐ近くにはあまりいないんですよねー
個人レベルで「ハイチ地震の犠牲者に寄付」とかしている人はいくらでもいると思うのですが(その程度であれば、いちいち人に言わないし)、「本気で努力する人 = 自分の力をフルタイム割いている人」としてみるとほとんどいない。
「私の周り」の範囲が狭いのはもちろんあるし、私たち世代は今から子育て期に入りとにかく先立つものが必要という世代的なものもあると思うのですが、ひとり見つけたのでご紹介。
INSEAD同級生、インド系カナダ人のS、サンフランシスコ在住。
両親は貧しいインド南部の地方からカナダへの移民、自身はトロントで生まれる。 Sと弟はトロントでカナダ人として育ったが、3年に一度ほど両親の故郷のインドの町(子供が靴を履いていないようなところ)に帰ると、親戚一同から「先進国に移住して富を得るというドリームを見事に果たした家族」として王様のような扱いを受ける、と言っていたのを覚えています。
 大学卒業後はサンフランシスコで10年間デロイトで戦略コンサルタントとして勤務(途中でinsead留学)。 ふいに去年デロイトを辞めたのでどうしたのかと思ったらfairtrade(サンフランシスコ本社)で働き始めました。 私は”フェアトレード”とは「公正な貿易」という概念・コンセプトだと思っていたのですが、しっかりした認証団体があったんですね。
大学卒業後はサンフランシスコで10年間デロイトで戦略コンサルタントとして勤務(途中でinsead留学)。 ふいに去年デロイトを辞めたのでどうしたのかと思ったらfairtrade(サンフランシスコ本社)で働き始めました。 私は”フェアトレード”とは「公正な貿易」という概念・コンセプトだと思っていたのですが、しっかりした認証団体があったんですね。
FLOというSが勤めるNPOは主に
- 国際フェアトレード基準の設定
- フェアトレード市場の開拓・促進
- 生産者への支援
- 現行の国際貿易の不均衡な仕組みを問い、より公平な貿易を促進するためのアドボカシー活動
を活動領域としていますが、彼は主に世界中の大企業(飲食・食品が多い)に対し、フェアトレードを採用してもらう交渉を担当しています。
最近ではアイスクリームのBen & Jerry’s案件とか。 →Ben & Jerry’s goes 100% Fairtrade
先日、ロンドンに出張で来ていたSと会ったのですが、「デロイトでは企業トップに経営戦略アドバイスをしていた。 Fairtradeでは同じように企業トップにアドバイスをしながら同時に社会を良くすることができて最高。 I love it!」とのこと。
世界的な戦略コンサルからNPOへの転身ということで気になるお給料については、「アメリカでは民間企業並みの給料が出るNPOもある」というお茶を濁したお答えでした。
彼のご両親がひたすら生活の改善を願ってカナダに移住を果たしたのに対し、彼の世代で「衣食足りる」と社会を良くする方向に意識が向いた、といういい例ではないでしょうか?
もうひとり似た例を知ってるので直接話を聞いたらまたご紹介します。
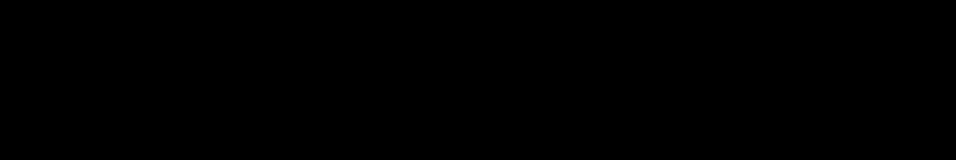

March 2nd, 2010 at 11:43 pm
la dolce vitaさん、「インドの衝撃」は切っ掛けになってもらえました(笑)?
日本でこのことが暫く前に話題になったんです。幾つかの記事があるんですが代表的なものを示します。
http://komazaki.seesaa.net/article/135762282.html
何でしょう、私はこういう「大御所感」というのがたまらなく嫌なんですね。恐らく「他人を助けることを外に出すんじゃない、黙ってやりなさいよ」という事だと思います。が、それは寄付や片手間ならそれで構わないんですが、それをある組織で実行するということになると、逆に上手く外へ発信しないと駄目なんですね。日本でこういったことが中々根付かないのはこういう「人を助けるのは影からそっと」というところが強いからなのかも知れません。
日本というのはまだまだ素晴らしいところがあって、例えばハイチやチリに地震と比べて阪神大震災では大規模な略奪や暴動は起きなかったことのような我慢強さ(は、最低の生活が出来ているからでしょうが)やいざと言う時の相互互助の高さはある。だから上手く変われば良い組織になると信じているんですが、どこにその仕掛けを作ればいいのか?が肝なんでしょう。
March 3rd, 2010 at 7:01 pm
>ドイツ特派員さん
フローレンス駒崎さんのブログは出たときに読みました、話題になってましたね。
わざわざ給料の話を最後に書いたのもそのためなんですが、NPOで働いている人が普通のmarket competitiveな給料をもらうことが当たり前、のような社会的な空気も大事かと思います。
March 3rd, 2010 at 9:57 pm
通常の経済活動と、社会を良くすることとは別物とは思いません。
先進国の恵まれたエリートに世界のリードを任せておけば、絶対世の中良くなるかというと、これも大いに疑わしい。
フェアトレードを謳っている認証機関が、本当にフェアなのかどうかという批判もあリうるわけで、私がよく一緒に仕事をする飲食食品大企業は、Fairtradeの生産者の区分の仕方が独断的で意味をなさないことがあると、ブツクサ言っています。
儒教的文化圏内に限らず、ビジネスマンの行う商取引を下劣な利己的行為としか考えない面々が数多いるため、企業はCSRを強調して「こんな良いこともやってますよ」と広報にやっきになります。その結果、ほら、本来の事業活動と社会善行とは別物であると自ら認めてるじゃないの、と受け取る人たちもいるでしょう。
しかしながら、経済とは「経世済民」の略のはずです。わざわざマックス・ウェーバーを持ち出さなくとも、テツオ・ナジタ著「懐徳堂-18世紀日本の徳の諸相」とか山本七平著「日本資本主義の精神」などが指摘するとおり、商取引とは欲望の追求として卑下されるべきものではなく、立派な倫理的バックボーンを備えたものだという認識が日本の思想伝統にあるわけです。
もちろんアメリカにも同じような考え方があり、WSJが毎年感謝祭とクリスマスに再掲する社説などにそれがありありとしていますし、Ayn Randが根強い人気を誇っているのも、彼女の資本主義のin-your-face defenceが、見事に自称善行者たちの虚偽のマスクを引っ剥がすことに成功していることにあると思います。
Do-gooderが全てマユツバだというつもりはありませんが、「良いことをしているんだ」というノリが、Some are more equal than othresに移行しないように心するべきだとも思います。
March 4th, 2010 at 6:32 pm
>tygertygerさん
>通常の経済活動と、社会を良くすることとは別物とは思いません。
>先進国の恵まれたエリートに世界のリードを任せておけば、絶対世の中良くなるかというと、これも大いに疑わしい。
それはそうですね、今回はメールのリクエストに答えるために、狭義に定義して知ってる人を探して紹介したので、「経済活動とは別物」とか「エリートに任せればいい」とか主張しているわけではありません。 あくまでケース・スタディです。
March 5th, 2010 at 1:18 pm
la dolce vitaさん、こんにちは。
メールを取り上げていただき、ありがとうございます。
そしてわざわざリクエストにお答えいただき、深謝です。
渡辺千賀さんの本で読んだのですが、シリコンバレーでは
企業で成功
↓
そのお金を元手に自分が社会のためになると思ったことをやる
(慈善だった、エンジェルだったり)
という好循環ができているみたいですね。
やはり現実にロールモデルがいるかどうかは相当大きな差なんだと実感いたします。
(書きながらサークルや部活で「チームの実力はエースの実力に大きく左右される」という経験則を思い出しました)
余談ですが、渡辺千賀さんもかかわっているNPOのツアーで来週シリコンバレーに行ってきます。
あまり予習をできてないのですが、とても楽しみです。
>tygertygerさん
レスポンスをいただき、ありがとうございます。
誤解のないように言いますと、経済活動が悪だと言っているわけではありませんし、
中国出身ということもあり、それが結果的に世界をより良くすることも体験したつもりです。
ただ、逆にその反動(Win-Winのビジネスではなく、以下に他を蹴散らすかを考える人が多いこと)も感じています。
私が言いたかったことは、二点
・ 視野を自分のコミュニティだけではなく、もっと広げられるのはある程度裕福な人の方が可能性が高い
・ それができる立場にある人にはぜひ自覚を持って少しでも全世界視点を持って自分なりの判断をしてほしい
ということです。
そして、少しでも「自分だからできること」を意識することで、今の日本に漂う「将来は暗い」という閉塞感を自分たちの手で取り払えるし、それが他の人にとってもいい循環になるんじゃないかと思っています。
ご指摘いただいたHowの部分ですが、
自分の他の欲求とのバランスで各人持っていただければいいと思っています。
経済活動のWin-Winを通してでもいいですし、フルタイムの慈善活動でもいい。
「いいことをしているんだから俺が正しい」という独善に陥らない注意はもちろん必要ですが、
多少人によってずれたとしても、「あるべき姿」を追求する姿勢を持つことは、みんなにとって世界をより住み心地の良いところにできるのではないでしょうか。
March 6th, 2010 at 7:57 pm
>任宜さん
どういたしまして、ご希望に沿えたかわかりませんが。
>やはり現実にロールモデルがいるかどうかは相当大きな差なんだと実感いたします。
そうですね、「何を当たり前と思うか」、環境は大事ですねー、つくづく。
>余談ですが、渡辺千賀さんもかかわっているNPOのツアーで来週シリコンバレーに行ってきます。
JTPAツアーですか? このブログを読んでる方にも何名かいらっしゃいますよ、過去に参加された方。
例えば(↓)。
http://www.ladolcevita.jp/blog/global/2009/11/post-277.php
楽しんできてください〜。 千賀さんによろしくお伝えください。
March 9th, 2010 at 5:35 pm
フローレンス駒崎さんのブログで引用されている方々の反応は、私も大いに?ですね。確かに、社会起業家を「キャリア」としてみてしまうと、マッキンゼー→NPOというような例が目に付いてしまい(それをひとくくりにするのも乱暴ですが)、ちょっとどうかなと思うのもわからなくはないです。
確かに、コンサル→NPO→HBS、という「キャリア」が周りにも結構いて、そのあとの行き先次第では、HBS・MBA受けするレジュメするためだったんじゃない?といううがった見方が出来なくもないです。ただ、フローレンスの存在で救われている友人も実際にいますし、駒崎さんや社会起業家を「キャリア」やはやりとして見るんじゃなくて、実際にどんなValue Propositionをフローレンスが提供してて(完璧じゃないにしても)、それで実際に助かっている人たちがどれだけいるのか、想像するほうが健全かなと思います。
ブログで引用されている「大御所」の人たちが、もし、事実・正しい認識に基づいて批判しているのだとすると、それはそれで興味ありますが。
March 10th, 2010 at 12:02 pm
>Playlandさん
ありがとうございます。 私も駒崎さんのブログで引用されている人の反応は全くわからなくもない、と思ってました。
>コンサル→NPO→HBS、という「キャリア」が周りにも結構いて、そのあとの行き先次第では、HBS・MBA受けするレジュメするためだったんじゃない?といううがった見方が出来なくもない
まさに、こういう人(↑)が今の時代はどうしてもいるので、「時代が違ったら違う道を選んだんじゃない?」という見方はおかしくない(人は時代というコンテクストの中で動いているので別にいいんですが)。
>実際にどんなValue Propositionをフローレンスが提供してて(完璧じゃないにしても)、それで実際に助かっている人たちがどれだけいるのか、想像するほうが健全かなと思います。
おっしゃる通り、NPOなのか営利団体なのかという器ではないと思います。
上記のブログの中では、NPOという器でFairtradeに就職した人を紹介しただけで、あまり詳細触れていないのですが、彼の場合マイクロファイナンスの会社を自分で立ち上げるために会社を辞めて、その直後に法改正で思った事業ができなくなったため、やはり就職し直すことにした、という細かい経緯があったのでした。