渡辺千賀さんに続いて(→こちら)、梅田望夫さんまで「あー、言っちゃったー」です。
残念に思っていることはあって。 英語圏のネット空間と日本語圏のネット空間がずいぶん違う物になっちゃったなと。
日本のWebは「残念」 梅田望夫さんに聞く(前編) (1/3)
日本のWebは「残念」 梅田望夫さんに聞く(前編) (2/3)
日本のWebは「残念」 梅田望夫さんに聞く(前編) (3/3)
IT Mediaのこの記事、読んだ瞬間、「また炎上するだろうなー」と思っていたら案の定ネット上でバッシングされている模様。 池田信夫さんも取りあげてました(→『梅田望夫氏の開き直り』)
気になったので梅田さんの記事で触れられていた『ウェブはバカと暇人のもの』を斜め読みしてしまった。 普通に読み物としては面白かったです(ブログをやっている身としては「ブログは一般人のどうでもいい日常」にドキッとした、笑)。
私自身は英語圏のネット空間も日本語圏のネット空間も必要と適正に応じて使い分けていて「物は使いよう」「ネットはあくまで道具」だし、ブログでいいことたくさんあるので「バカと暇人のもの」とはあんまり思っていないのですが、反応を見ていると、梅田さんが言わんとしているところと全然違うところに反応している人が多いことに気づきました。
「日本発でいいものができないってのか?!」
という趣旨で、ちょっと前の「日本はダメだ論」にすり替えられてしまっているものが多いような。
梅田さんの真意については海部未知さんの感覚が近いです(↓)。
Tech Mom from Silicon Valley:梅田氏と「アテネの学堂」
で、ここまでは前置きだったのだが、「日本発でいいものができないってのか?!」について私が以前から思っていたことを。
インターネットの世界に限っていうと、英語圏発以外でグローバルになったものってあるのかなー?(英語圏といえど、発祥地は地理的にはアメリカなんだけど、わざわざ「英語圏」としたには訳がある、下記参照) だいぶ前の話だけど、IM (Instant Messenger)はイスラエル企業でした(2006年、AOLが買収)。 それ以外、聞いたことないんだけど、フランス語圏発とかも。
そして英語圏SNS代表であるFacebookより発達した特定語圏SNSってのも聞いたことないし、Amazonよりすごい特定語圏オンラインストアってのも聞いたことない(Amazonの事業領域はe-コマースから大きく拡大したけど、それは別の話)。
つまりインターネットという強くネットワーク外部性(*1)が働く分野では、普遍語としての英語環境(→『英語のひとり勝ち』)で商品・サービスを世に出すのが一番、(市場が大きいため)競争が激しい分、世界で最も強いもの・優秀なものが残っていくという自然界の論理と同じなのだと思います。 クリティカル・マス(*2)に達するスピードも速いし。
*1 IT情報マネジメント用語辞典:ネットワーク外部性
*2 IT用語辞典バイナリ:クリティカルマス
非常に短絡的にまとめると、英語人口と日本語人口の差であって(英語人口というのは英語を母国語とする人だけでなく英語を操るすべての人を含む)、「日本にいいものがある」と胸をはるのであれば、初めから世界を目指せばよいのでは?(と言う話は以前も『Red Herring 100 Asia』に書きました)。
一昨日も書いたけれど、私は「日本の方が何年も世界の先を言っている、日本の技術の方がどう見ても優れている」と言われ、現代の日本人の生活に欠かせないものになっているにも関わらず「ガラパゴス」などと呼ばれている技術の海外進出を行い、世界制覇とは程遠い結果に終わったのを2回も経験しているので、日本の技術のタネが優れていることには何の疑いも持っていません。
重要なのは「これは良い技術なんです」という、私も昔は交渉相手に対して何度も繰り返したこの言葉、良い技術であることの証明だけじゃダメなんだなー、ということ。
日本人が苦手な「いち早く商品化して、いち早く世界市場でテストする = ビジネス・ディベロップメント」「超スピードの成長企業を経営する = ベンチャー経営」「VCなどリスクマネーを上手に使う = 財務戦略」あたりができる人を外から引っ張ってきて(もしくは、そういう人がいるところに行って)、ひとつでもふたつでも「日本発技術」の成功例を積み重ねていくのがいいのではないかと。
私は日本の大企業には、これは結構難しいと思っているんだけど、ベンチャーは初めから失うものがないので、できそうな気がします。
一例をあげると、最近急速に普及しているSlideShare(YouTubeのPower Point版)は本社はサンフランシスコにあるもののバックエンドや開発は全部インドなんだそう。
創業者のプロフィール見てもアメリカ人なのかインド人なのか、白黒つけようとすることが無意味な気がするプロフィールです。
同じような意味で、『東京発Genkiiなベンチャー』は面白いと思った次第。
日本のベンチャーよ、世界を目指そう♪
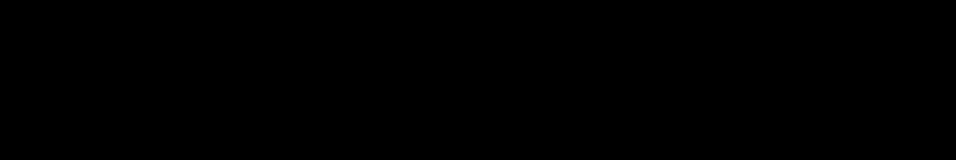

June 5th, 2009 at 12:35 pm
スカイプはルクセンブルクの企業でしたっけ。エストニアで開発したみたいですね。
あとLinuxは、フィンランド発と呼んでも良いような気がします。
あまり関係ないですが、テトリスがソ連発と知った時は驚きました。
改めて考えてみると、ほとんど英語圏のサービスですね。
世界市場でのテストがやりやすくなると、少しは状況が変わってくるのかもしれません。
June 6th, 2009 at 9:29 am
日本の技術は、芸が細かくて、完成度が高いと思います。
ただ、それをアメリカから見てると、そこまでやらなくてもなーとか、
採算取れてなさそう(取れない)だなぁ、としばし考えるときがあります。
完璧主義じゃないですか。最初から。融通が後で利きにくい。
アメリカは、出たとこ勝負!売りながら直したり、人気のある機能や
ツールはどんどん後から増やしていったり柔軟ですよね。
どっちもよしあしですけども。
ビジネスモデルと商品の完成度、パイの大きさのバランスのいい
日本のベンチャーが出てくるとうれしいですね~。
June 6th, 2009 at 10:39 am
>yosukeさん
エストニアとかフィンランドとか小国は初めから自国市場だけなんて考えてないですからね。
だからこういうのが出てくるんだろうなー 技術はどこの国発でもグローバルにできるよい例ですね。
>世界市場でのテストがやりやすくなると、少しは状況が変わってくるのかもしれません。
そんなに世界市場でのテストがやりにくいんですか? 素人目から見るとeasier than everというか、こんなにやりやすくなった時代もないと思うんですが。
>hirokoさん
>アメリカは、出たとこ勝負!売りながら直したり、人気のある機能やツールはどんどん後から増やしていったり柔軟ですよね。
そのへんを「いち早く商品化して、いち早く世界市場でテストする = ビジネス・ディベロップメント」の人を外から入れて(別にアメリカじゃなくてもいいけど)、スピード速めたらいいのでは?という趣旨です。
最近はますますスピード命になってきて、この最中にいる人は寿命が縮まりそうですけどね。
June 7th, 2009 at 1:41 pm
日本の技術は高いと評判と実績はデータで見てもわかりますしね。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/files/1402-027/graph.pdf
知的生産性の高さを維持する基準のひとつが特許とすると取得数では日本は
世界トップレベルに位置しています。
今後の世界経済をひっぱいっていくであろう、環境やエネルギー、バイオの分野ではダントツの1位。
しかし、市場にマッチしていない(市場が求める以上のものなど)、市場のリーダーシップをとって
いけてない。 業界スタンダードを作る風土やネゴが苦手。la dolce vitaの http://www.ladolcevita.jp/blog/global/2009/06/—2.php にも発言されておられますように。(フランスはルールを作るだけでなく、国際標準にするのが上手。)
こういう力は何かする時に必須になっているかと思います。
市場の変化に対応する臨機応変力とデフォルト力(業界のスタンダード)は
世界で勝負するには今後ますます必要になってくるかと思いました。
制度を作っていくなどは学校やマニュアル本では教えてくれない「仕事力」の
一つなのかなと。
June 8th, 2009 at 9:45 am
>しんさん
>制度を作っていくなどは学校やマニュアル本では教えてくれない「仕事力」の一つなのかなと。
たしかに学校では習わないですねー
いかに周りの人を巻き込んでいくか、まさに人間力と政治力の世界ですから。 「机上の空論」の対極に位置する「ストリート・スマート」が必要で、それこそストリートで身につけていくしかないので、言葉にしなくても「あうんの呼吸」でわかってくれるような環境にいると身につかないんじゃないでしょうか?
June 9th, 2009 at 9:44 pm
la dolce vitaさん、
この記事は旅行もとい出張中にも何度か読みました。内容についてはまた別途考えたいと思っているんですが、私の思いとしては二つです。
1.梅田さんが言いたかった内容は、別に日本とアメリカ(英語圏と言っているがあえて限定して)を比較しなくても、別におかしくはない内容だったのではないか?であるのに、どうもアメリカを例に出してしまったがために、「またアメリカかよ!」という反発が先に来てしまい、炎上状態になってしまったんじゃないでしょうか?
2.ただ、皆さんが反応していないところに反応すると、梅田さんが「僕は長期的なことに興味がある」と言いながら、高々ここ10年くらいのインターネットで出た現象に対して断定的な駄目出しをしていることに違和感があるんですね。私が過ごしている製造業とスピードが違うのかも知れませんが、文化を変えるくらいのことは相当時間が掛かるのと、寧ろ短時間での成果よりじわじわとした長時間の成果の方が長続きするという気がしています。
3.少なくとも一般の人がブログを通じて繋がることが増えていること自体、肯定すべきことだと思います。そりゃ私のブログなどは彼がいうところの「自分を高めるため」というブログのかけらにもなっていませんが、それでも、そこから人の関係が増える、ということで何らかの触媒作用は増えているわけで、そういう部分は彼が考えている「ハイブロウ」なところとは別にじわじわと広がっているはずです。
先駆者が本当につらいのは、自分が手がけた結果を自分が手を掛けている間には手に出来ないことが多いということだと思います。梅田さんには、「まあまあ、紆余曲折はありますよ」と、僭越ながら肩でも揉んであげたいな、という感じですね。
だめだ、何かまとまりがないですねえ。やっぱ頭の限界か…。
June 10th, 2009 at 3:18 pm
>ドイツ特派員さん
>どうもアメリカを例に出してしまったがために、「またアメリカかよ!」という反発が先に来てしまい、炎上状態になってしまったんじゃないでしょうか?
それは思いました。 昨日も会った友達と「やっぱり日本人はそんなにアメリカ意識してるんだねー」という話になった。
>少なくとも一般の人がブログを通じて繋がることが増えていること自体、肯定すべきことだと思います。
私もほんとそう思います。 だから単純に「ウェブはバカと暇人のもの」とは思ってないのですが。 はてなや2chという一部の現象のような気がするんですけどね。